前回、巨大なメガトレンドは1社では解決不可能な「共通課題」であると述べた。今回は、その課題を「T=技術」と「B=仕組み」の側面から深掘りする。なぜ、かつて日本の強みであった「自前主義」が、今やイノベーションの「壁」となっているのか。その構造を解説する。
はじめに:なぜ「自前」では無理なのか?
第1回では、メガトレンドという巨大な社会課題に立ち向かうため、オープンイノベーションが不可欠であると提示しました。
JOIAは、メガトレンドをその発生要因から3つに分類しています。
- T (Technology): 技術進展
- B (Business): 新しい仕組み
- D (Design): 政策・社会的価値観
今回は、このうちT(技術)とB(仕組み)がいかに複雑化し、1社単独での対応=「自前主義」を困難にしているか、その実態を見ていきます。
T(技術)の壁:「死の谷」を1社で越えられますか?
まず、T=技術の課題です。 JOIAの分析レポートでは、「先進医療(ゲノム編集)」、「次世代情報インフラ(量子コンピューター)」、「次世代素材」などがTに分類されます。
これらに共通するのは、技術がかつてなく高度化・複雑化し、基礎研究から社会実装までに要する時間とコストが膨大になっていることです。
例えば、AI創薬や再生医療は、一つの技術だけで完結しません。 バイオロジー、化学、情報工学(AI)、さらには製造プロセス技術まで、多様な領域の最先端の知見が不可欠です。
かつては、企業の中央研究所がその多くを担うことができました。 しかし今、これら全ての専門領域で世界最高レベルの知見を「自前」で揃え続けることは、いかなる大企業にとっても非現実的です。
結果として、大学や研究機関で生まれた素晴らしい技術シーズ(T)が、社会実装(B)に至る前の「死の谷」を越えられず、眠ったままになっているケースが後を絶ちません。 この「死の谷」を1社で越える体力も、多様な知見も、もはや持ちきれないのです。 だからこそ、産学官の壁を越えた連携が、技術イノベーションの最低条件となります。
B(仕組み)の壁:業界横断の「ルール」を1社で作れますか?
次に、B=仕組みの課題です。 レポートでは「MaaS(Mobility as a Service)」、「スマートシティ」、「D2C」、「シェアリングエコノミー」などがBに分類されます。
これらに共通するのは、1社の努力ではビジネスモデル自体が成立しないことです。
例えば、MaaSを考えてみましょう。 一人のユーザーが、出発地から目的地までシームレスに移動するという体験。 これを実現するには、鉄道、バス、タクシー、シェアサイクルといった複数の交通事業者のデータ連携が不可欠です。
A社の鉄道アプリ、B社のバスアプリ、C社のタクシーアプリがバラバラに存在していては、MaaSという「新しい仕組み(B)」は成立しません。 自社の顧客、自社のサービスだけを囲い込む「自前主義」は、MaaSの利便性を根本から破壊してしまいます。
スマートシティやD2Cのプラットフォームも同様です。 これらは、**業界の垣根を越えた「データ連携」や「共通プラットフォームの構築」**という、いわば新しい「交通ルール」作りそのものです。 そのルールを1社だけで作り、他社に従わせることは可能でしょうか?
それは多くの場合、不可能です。 むしろ、競合他社とも対話し、共通の仕組み(B)を構築するという協調的なアプローチこそが、結果として市場全体を創造し、自社の利益にもつながるのです。
結論:「自前主義」から「協調」へ
T(技術)も、B(仕組み)も、現代のメガトレンドは1社で抱えきれるほど単純ではありません。
- Tの課題は、産学官の連携でしか越えられない。
- Bの課題は、競合他社を含む業界連携でしか構築できない。
「自前主義」は、もはや強みではなく、イノベーションを阻害する「壁」となりました。 では、どうすれば利害の異なる他者と「協調」し、共にイノベーションを生み出せるのでしょうか。
次回は、その最大の鍵となる第3の力、D=Design(社会課題)について解説します。 Dこそが、バラバラのプレイヤーを束ねる「共通の大義」となるのです。


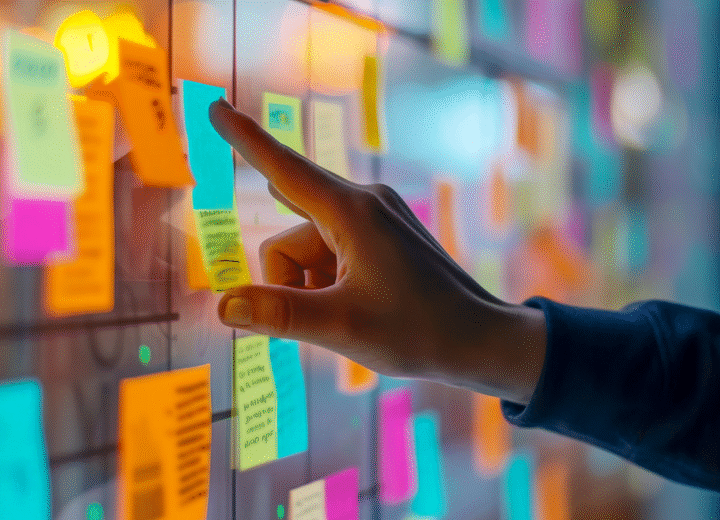

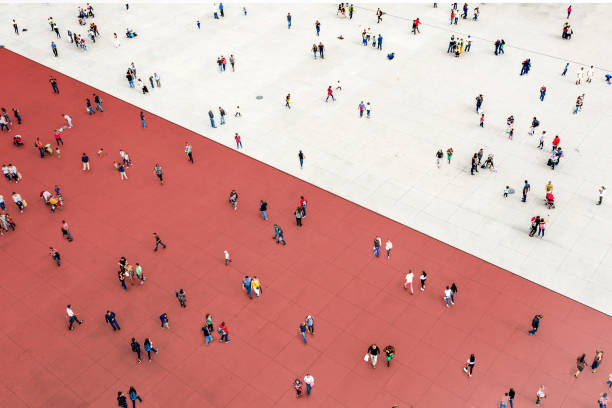









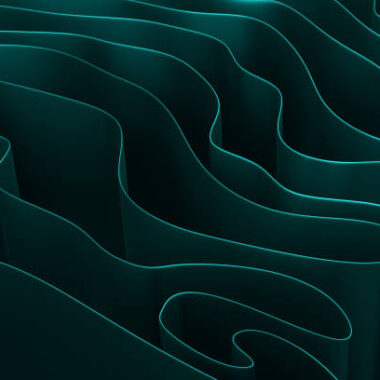
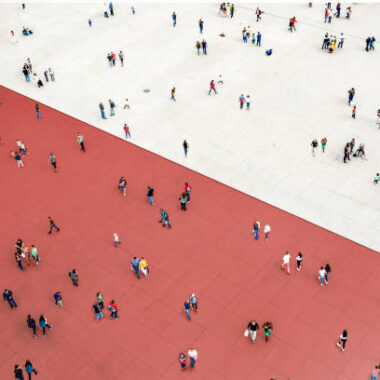


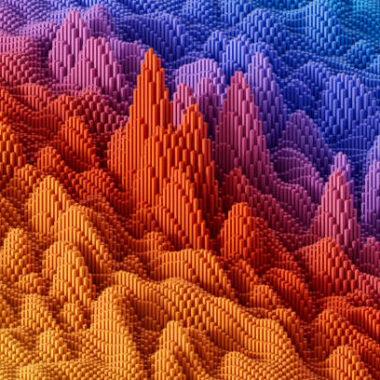

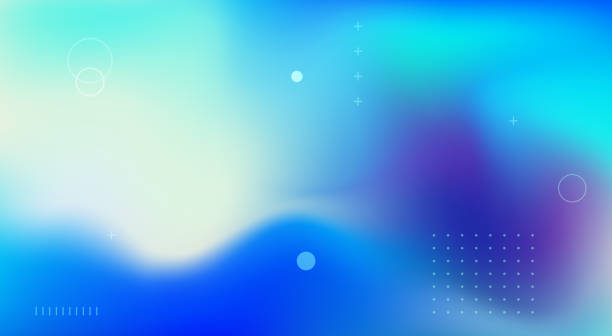




コメント