設立者・代表理事 青山 武史
1. なぜ、日本企業は勝てなくなったのか?
日本企業は、今、大きな岐路に立たされています。個々の技術力や現場の品質は依然として世界トップクラスであるにもかかわらず、なぜグローバルなイノベーション競争で存在感を失いつつあるのでしょうか。
多くの経営者や実務家と対話する中で、私はその根源が「自前主義の罠」と、それによって引き起こされる「イノベーションのジレンマ」にあると確信しています。
「自前主義」—すなわち、研究開発から製造、販売に至るまで、すべてを自社で完結させようとする思想は、かつて日本の「ものづくり」を世界一に押し上げた成功モデルでした。しかし、市場の変化が激しく、AI、GX(グリーン・トランスフォーメーション)、ヘルスケアなど、あらゆる技術が複雑に絡み合う現代において、この成功体験が、皮肉にも私たちの足かせとなっているのです。
一社ですべての技術をキャッチアップし、すべてを内製化することは、もはや不可能です。物流業界が直面する「2024年問題」のような社会課題も、一社の努力だけで解決できるスケールを遥かに超えています。
2. 「出島」と「CVC」が機能しない本当の理由
この問題に気づいた多くの企業が、次なる一手として「オープンイノベーション」を掲げました。シリコンバレーに「出島」となるイノベーション拠点を設け、あるいはCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)を設立し、スタートアップとの連携を模索してきました。
しかし、その多くが期待した成果を上げられていないのはなぜでしょうか。
私は、その原因が「本社の免疫システム」と「KPIの誤設定」にあると考えています。
「出島」やCVCがどれほど有望な技術やパートナーを見つけてきても、それを本社の既存事業部(=母艦)に持ち込んだ途端、強烈な拒絶反応(免疫)に遭います。「我々のやり方と違う」「短期的な売上にならない」「リスクが不明確だ」—。これらの声は、既存事業を最適化し守ってきた優秀な社員ほど強く発せられます。
さらに、CVCや新規事業担当部門に、既存事業と同じ「短期的な売上」や「ROI(投資対効果)」をKPIとして課してしまう。これは、イノベーションの芽を、その初期段階で摘み取ってしまっていることに他なりません。
3. 今、求められる「協業の作法」
真のオープンイノベーションを実現するためには、スタートアップと対等に渡り合うための「協業の作法(ルール)」を、大企業側が学ぶ必要があります。
作法1:アセットを「開放」し、「非対称性」を認識する
協業とは、対等な分業ではありません。大企業が持つ、スタートアップが逆立ちしても手に入らない資産—それは「販売チャネル」「膨大な顧客データ」「ブランドの信用力」「量産化技術」です。 大企業がなすべきは、これらのアセットを「開放」すること。そして、スタートアップが持つ「スピード」と「尖った技術」を、自社のルールで縛り付けないことです。協業とは、互いの「非対称な強み」を交換することなのです。
作法2:「戦略的学習」をKPIに設定する
初期段階の協業において、KPIは「売上」であってはなりません。KPIは「戦略的学習」であるべきです。 「このパイロット(実証実験)で、市場の仮説は検証できたか?」「この技術は、我々の顧客に本当に響くのか?」「あえて『参入しない』という賢明な判断ができたか?」—。 たとえプロジェクトが中止(Kill)になったとしても、この「学んだデータ」こそが、次なるイノベーションの種となる最も価値ある資産です。
作法3:本社の「免疫」を抑える「特命役員」を置く
スタートアップとの協業プロジェクトは、必ず本社の既存事業部と摩擦を起こします。その「免疫反応」を強制的に抑え込み、実証実験を断行させる「強力な権限」が必要です。 それは、CVC担当役員であると同時に、既存事業のキーマン(例:CSO(最高戦略責任者)やCHRO(最高人事責任者))であるべきです。その役員が、「このプロジェクトは、短期的な売上ではなく『戦略的学習』として全社で取り組む」と宣言し、既存事業部のKPIにも「協業の推進度」を組み込む。このトップダウンの「覚悟」こそが、協業の成否を分けます。
4. JOIAの役割—「実践知」を共有する場
この組織変革と文化の刷新は、一朝一夕で成し遂げられるものではありません。だからこそ、私たち日本オープンイノベーション協会(JOIA)は、この変革を志す企業のための「プラットフォーム」として設立されました。
私たちは、単なるマッチング(PARTNER)を行うだけではありません。 不確実な未来を見据えるための「シナリオプランニング」(PROGRAM)を通じて戦略眼を養い、そして何より、本稿で述べたような「協業の作法」や「実践知」を共有するコミュニティ(PLATFORM)を提供します。
日本の「創造力」は、決して枯渇していません。それは今、企業の壁の中に「閉じ込められている」だけです。 私たちと共に、その壁を越え、日本から世界を変革するイノFベーションの「奔流」を創り出しましょう。


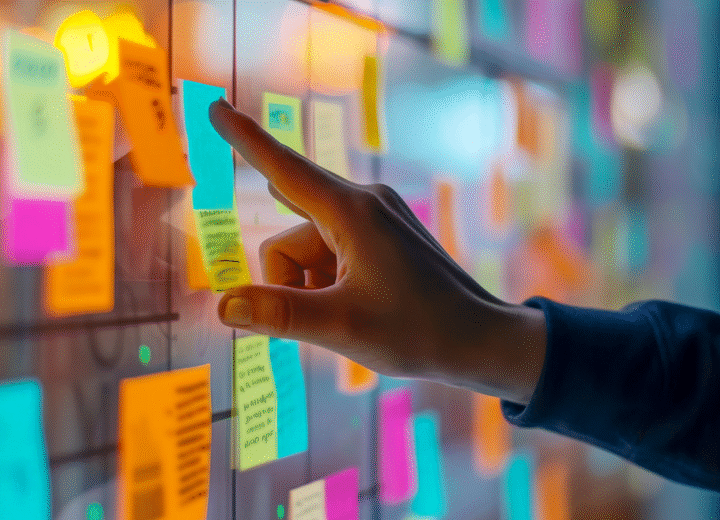

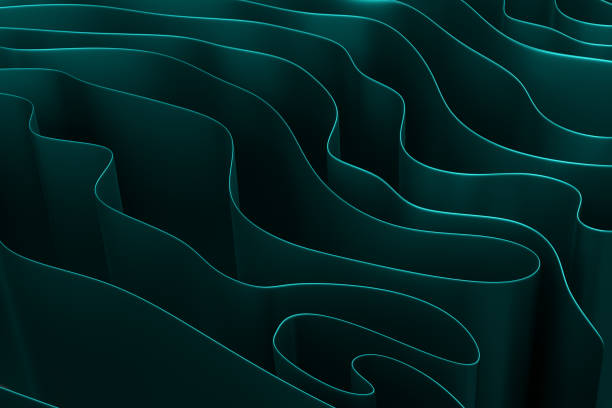







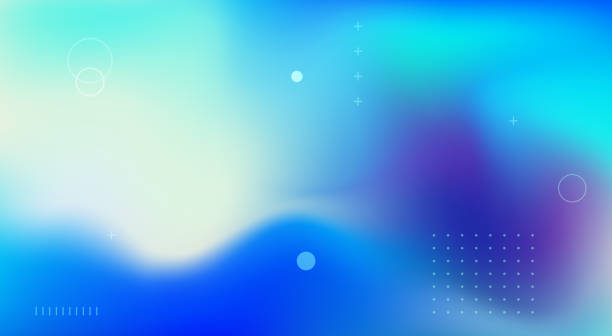


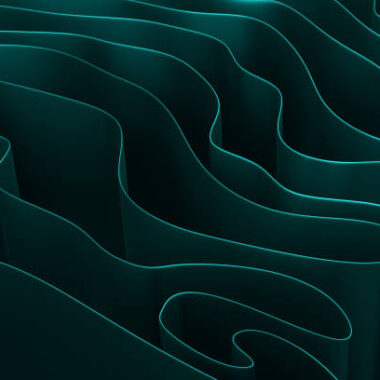



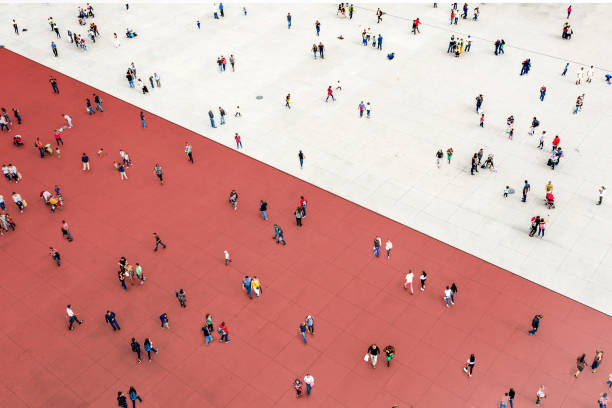





コメント