前回、T=技術とB=仕組みはあまりに複雑化し、1社単独では対応できない「壁」となっていると解説した。しかし、利害が反する競合他社が、なぜわざわざ協力しなくてはならないのか。その最大の推進力こそが、第3の力「D=Design(社会課題)」である。
はじめに:「協力」は綺麗事か?
T=技術も、B=仕組みも、もはや1社では限界だ。 そう言われても、多くの企業担当者はこう思うでしょう。 「とはいえ、競合は競合だ」「協力するメリットが、競争するデメリットを上回らなければ動けない」と。
それは当然の論理です。 では、その「協力するメリット」を凌駕する、強力な動機はどこから生まれるのでしょうか。 それが、JOIAが分類する3つ目の力「D=Design(社会設計・価値観)」です。
D (Design):社会が求める「あるべき姿」
D=Designとは、JOIAの分析レポートにおける**「3:政策や社会的価値観の変化」**に該当します。
- 脱炭素エネルギー・モビリティ
- 資源の循環・ロス削減
- 社会インフラ保全技術、防災テック
- 多様な価値観の尊重、アニマルウェルフェア
これらは、TやBとは決定的に性質が異なります。 TやBが「どうやって儲けるか」という個社の利益に直結しやすいのに対し、Dは「どうあるべきか」という社会全体の共通課題である点です。
私たちは、このDを「社会の再デザイン」と捉えています。 「持続可能な社会をどう設計するか」「人々がより良く生きられるルールをどう設計するか」という、公共性の高い問いそのものです。
「共通の課題」が「共通の大義」となる
なぜ、このDがオープンイノベーションの鍵となるのか。 それは、Dが**「共創のための大義」**、つまり共通の目的となるからです。
「脱炭素」というDは、自動車メーカー1社、あるいは社会全体にとっての「共通の課題」です。 「資源循環」というDは、素材メーカー、家電メーカー、小売、自治体すべてに突きつけられた「共通の課題」です。
これらの課題は、1社の利益追求(TやB)とは次元が異なります。 放置すれば、社会基盤そのものが揺らぎ、市場そのものが成り立たなくなる可能性すらある。 この**「共通の危機感」と「あるべき未来像の共有」**こそが、利害の異なるプレイヤーを同じテーブルに着かせる最大のエンジンとなります。
「競争領域」と「協調領域」
Dという「大義」が見えると、これまで「すべてが競争」だった領域に、明確な線引きが生まれます。 それが**「競争領域」と「協調領域」**の分離です。
- 競争領域: 製品の魅力、価格、ブランド、サービス品質など、各社が顧客獲得を競い合う領域。
- 協調領域: 業界共通の基盤、ルール、基礎研究など、市場全体を成立・発展させるために協力する領域。
D=社会課題は、まさにこの「協調領域」を生み出すのです。
例えば、「脱炭素」というD(大義)があるからこそ、競合する自動車メーカー同士が「充電インフラの規格標準化(B)」や「バッテリーリサイクルの基盤技術(T)」といった協調領域で手を組むことができます。 規格がバラバラでは市場が立ち上がらず、全員が損をすることが分かっているからです。
Dは、企業が「競争」の論理を一時停止し、「協調」へと踏み出すための、最も強力な理由付けとなります。
結論:Dが大義となり、TとBの協業を促す
T(技術)とB(仕組み)が1社で限界を迎えた今、それらを乗り越える唯一の道がオープンイノベーションです。 そして、その扉を開く鍵こそが、D(社会課題)という「共通の大義」です。
- Dが協業の**「目的(Why)」**となり、
- TとBが協業の**「手段(How/What)」**となる。
JOIAは、このDという大義のもと、産学官の垣根を越えた連携を生み出す場です。
次回は、このB×D×Tの3軸で分類したメガトレンドの全リストを公開します。 そして、その「協業の地図」を使い、自社に足りないピース、つまり「協業すべきパートナー」を見つける方法を解説します。


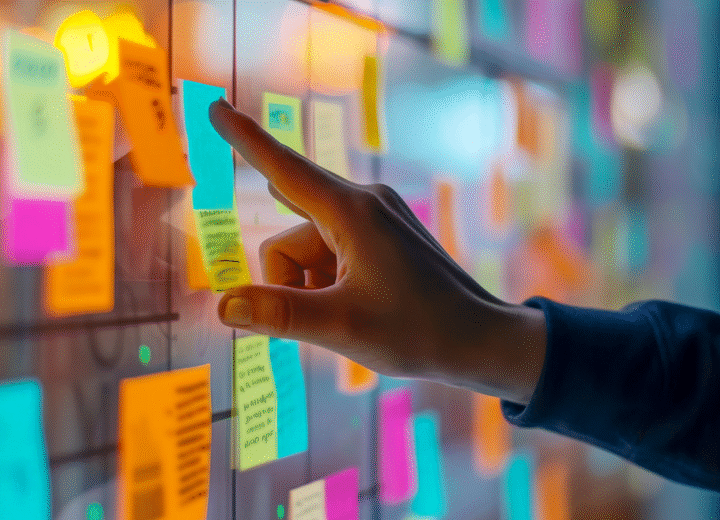
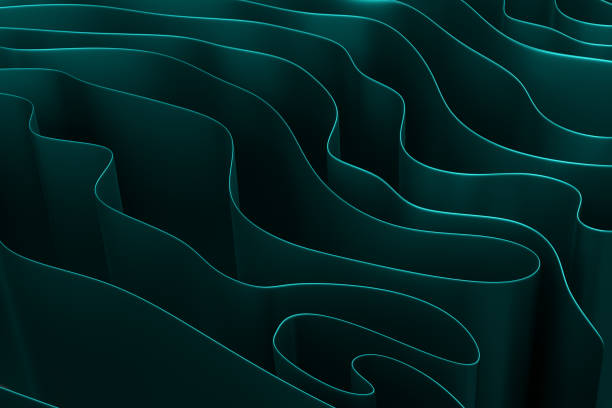



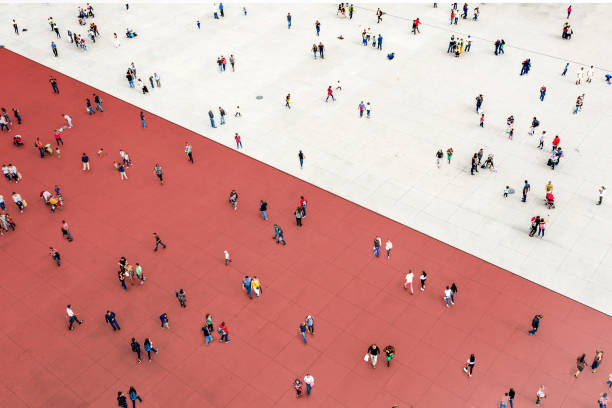







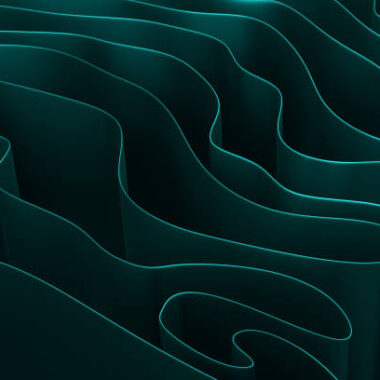



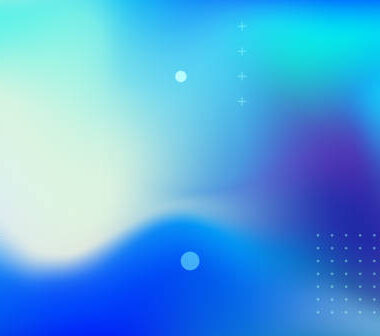
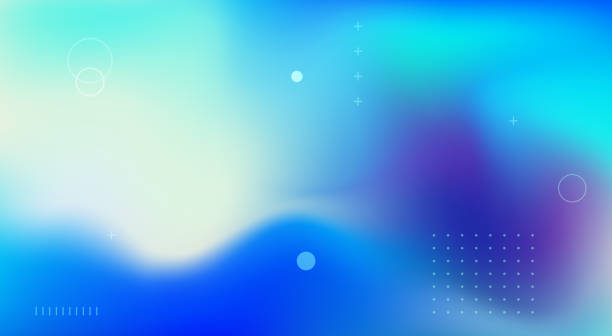


コメント