連載最終回は、JOIAが提唱する「協業の必要性」を「電気自動車(EV)」というテーマで具体的に解き明かす。EVの社会実装は、なぜ1社の天才的な企業だけでは不可能なのか。そのエコシステム構造を、T・B・Dの3つの「壁」から分析する。
テーマ設定:「EVの社会実装」という巨大な壁
これまで、メガトレンドという「共通課題」を解くには、オープンイノベーションが不可欠だと解説してきました。 その最大のケーススタディが「電気自動車(EV)」です。
「EV」と聞くと、私たちはテスラのような特定の「天才的な企業」のイノベーションを思い浮かべがちです。 しかし、JOIAは、**「EVを作ること」と「EVが普及した社会を実装すること」**は、まったく次元の異なる課題だと考えています。
EVの社会実装は、1社の努力では到底乗り越えられない、3つの巨大な「壁」に直面しています。
T(技術)の壁:1社で背負いきれるか?
まず、T=技術の壁です。 EVの性能は、バッテリー技術に依存します。より安全で、より高容量な「次世代電池」の開発。そして、使い終わった「バッテリーのリサイクル」技術。
これらの基礎研究開発には、莫大なコストと長い時間がかかります。 世界中の自動車メーカー、電池メーカー、素材メーカーが巨額の投資を行っていますが、1社がすべての領域で勝ち続けることは不可能です。
むしろ、基礎研究の領域では産学官が連携し、リサイクル技術のような社会基服(インフラ)に近い領域では業界で協調しなければ、このTの壁は越えられません。
B(仕組み)の壁:業界標準なくして普及なし
次に、B=仕組みの壁です。これが最も分かりやすい「協業」の必要性を示しています。 それは**「充電インフラ」**です。
もし、自動車メーカーA社、B社、C社が、それぞれ独自規格の充電プラグを開発・推進したらどうなるでしょうか? ユーザーは、メーカーごとに異なる充電スタンドを探さねばならず、利便性は最悪です。市場は混乱し、EVの普及そのものが止まってしまいます。
これは典型的な**「協調領域」**です。 充電インフラの規格(B)は、各社が「競争」する領域ではなく、業界全体で「協調」して標準化すべき領域です。 業界標準という「共通の仕組み(B)」を作って初めて、各社は「車の魅力(T)」という「競争領域」で正々堂々と戦うことができるのです。
D(社会)の壁:これはもはや「自動車」の問題ではない
最後に、D=社会設計の壁です。 EVの普及は、自動車業界だけでは完結しない、社会システム全体の課題です。
- 電力網との連携: 数百万台のEVが同時に充電を始めたら、電力網はパンクします。電力会社と連携し、充電時間を分散させる「スマートグリッド(B/T)」の仕組みが不可欠です。
- 都市計画との連携: 充電インフラをどこに設置するか。これは都市計画や建設業界、自治体(D)を巻き込んだ課題です。
- 資源・廃棄の問題: バッテリーに使われるレアメタルの問題や、廃棄バッテリーの処理問題(D)は、法規制(D)とも密接に関わります。
これらは、もはや1つの業界で解ける問題ではありません。 自動車、エネルギー、IT、素材、建設、そして官公庁。 これらのセクターを横断したオープンイノベーションなしに、EVが走る未来は実現しないのです。
JOIAの結論:未来は「共創」によってのみ実装される
EVの未来は、1社の「天才」が作るものではありません。
充電規格の標準化(B)で協調する競合同士。 次世代電池の研究(T)で連携する企業と大学。 そして、電力網や法制度(D)で協働する異業種と行政。
EVの社会実装とは、こうした無数の「オープンイノベーション」の集合体なのです。
日本オープンイノベーション協会(JOIA)は、こうした「1社では解けない課題」に立ち向かう企業、大学、官公庁を繋ぎ、セクターを越えた「共創」を生み出すハブです。
社会課題を「共通の大義」として、共に未来を実装しませんか。
(本連載 完)


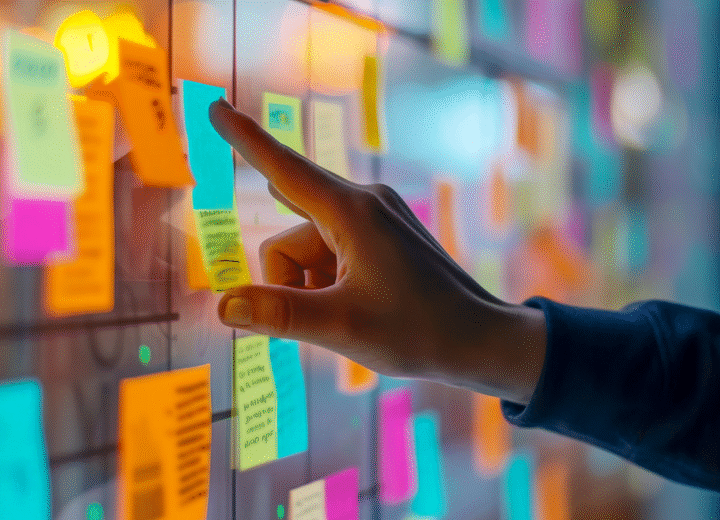



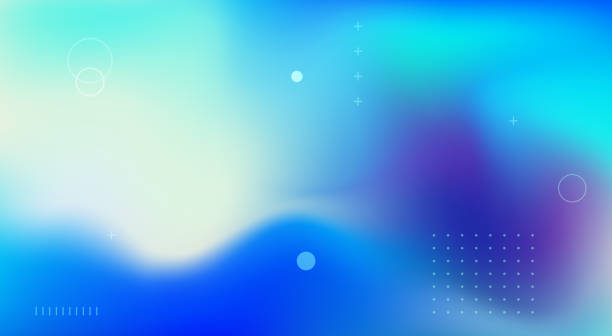


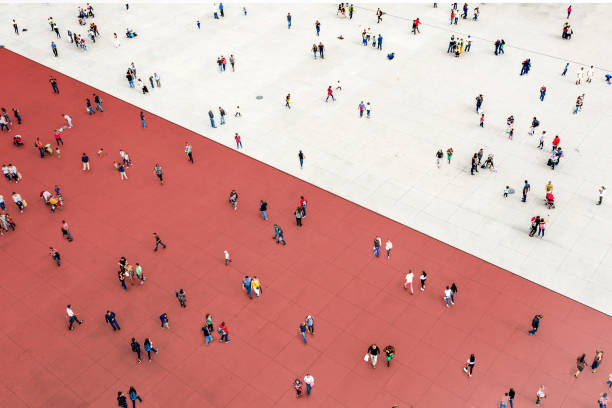
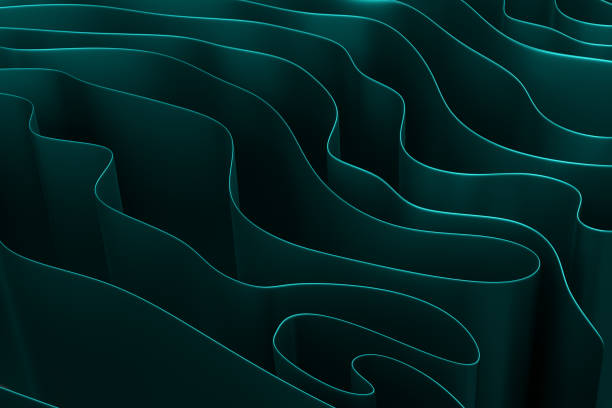




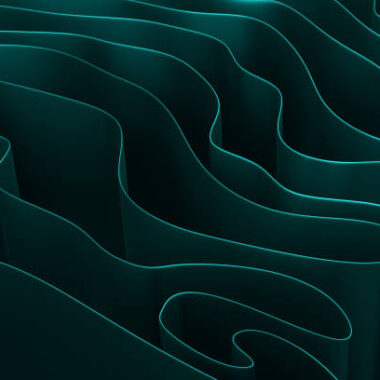


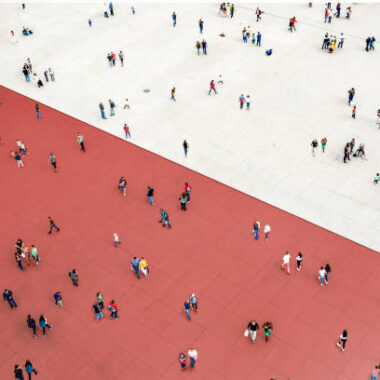







コメント