理論とはWhyに応えること
私たちは3C、SWOTなどの分析方法で企業の経営を理解しようとする。しかし、それだけでは不十分だ。では何が足りないのか。それは経営理論である。3C、SWOTなどのフレームワークはWhatに対してしか応えようとしない。しかし、コーネル大学のサミュエル・バチャラクの論文で「理論」について下記のように定義づけている。
“The primary goal of a theory is to answer the questions of how, when, and why, unlike the goal of description, which is to answer the question of what.”
「理論の主目的は「何が(What)」を記述するものではなく「いつ(When)」「どのように(How)」何故「Why」に応えること」
(Bacharach, 1989, pp.498.)
このように理論とは「何」ではなく「何故」に応えることを目指す。まず、Howとは「X→Y」のような因果関係のことだ。例えば主要な経営理論のひとつ、リソース・ベースト、ビュー(RBV)には、「企業の経営資源に価値があり稀少なら(X)、その企業を競争優位を獲得する(Y)」という有名な命題がある。これはXがYに影響を与え、しかもXが高まればYも高まるので、その関係はプラスであるということだ。このような関係を示すのがHowの応えることになる。
Whenは、その理論が通用する範囲を表す。ここでのWhenとは、学者の視点でどのように理論を当てはめるかという意味を示す。専門用語では「バウンダリー・コンディション」という。例えば、理論は大手企業に当てはまっても、スタート企業に当てはまらないこともあるかもしれない。ここで重要なのは「だから理論は役に立たない」と短絡的に考えないことだ。理論が持つ仮定・条件から、その適応範囲を明確にすることでWhenに応えることになる。そして最も重要なのが理論がWhyに応えるものであることだ。「X→Y」にような因果関係を示しても「何故そうなのか」が説明されなければ、それは理論ではない。そして企業は人の集合体という見方がができ、企業がビジネスを行うものだから「人は本質的にどのように行動するのか」の基本原理がなければ因果関係は論理的、整合的に説明できない。そのように説明ができなければ納得感を持って人が動くことはないのである。
1社だけに当てはまる法則には関心がない
さらに、これらの理論から得られた命題・仮説が「本当に真理に近いのか」を検証していく作業も必要になる。それを実証分析(empirical analysis)という。社会科学の一つである経営学は「科学」を目指している。科学の主要目的は「真理の探究」である。それは物理学などの自然科学と変わらない。すなはち、「なるべく多く企業、組織、従業員、経営者、ビジネスパーソンなどに普遍的に当てはまりうる、ビジネスの真理法則(How・When・Why)」を見つけることが最大の命題だのだ。少なくとも世界の経営学はそうなっている。たとえば、経営学は「1社だけに当てはまる法則」に関心がない。たとえばトヨタ自動車がいくら素晴らしくとも、それがトヨタにしか当てはまらないのならば意味がない」と見なす。トヨタ式のカンバン方式、会議手法、ノートの取り方に至るまで優れたフレームワークはあるが、これらに汎用性、普遍性がどこまであるのかは疑問が残る。エリックリース著「リーンスタートアップ(THE LEAN STARTUP)」はムダのない起業プロセスでイノベーションを生み出す手法として、多くの企業に受け入れられた。この書籍に「5つのなぜ」というテーマがある。問題に直面した時、5回の何故を繰り返し、プロセスを進化させていくことで、本当のところ何が起きたのか(真因)を明らかにする方法が示されている。これはトヨタの従業員が行っている手法を転用したものだが、汎用性、普遍性が高いと言える。
したがって経営学では様々な企業データ、経営者のデータ、心理実験データ、事例データ、コンピュータ・シュミレーションなどの実証実験を通じて、その理論が現実のビジネスの真理に本当に肉薄しているのかを検証する。この理論と実証は科学の基本であり、そして日本いオープンイノベーション大学が紹介する世界の経営理論は、この実証実験をくぐりぬけてきた理論と言える。
Whyの「説明」「納得」がなければ、人は動かない
現実のビジネスは非常に複雑である。多様な要素が絡み合い、多くのステークホルダーが関わっている。一つのビジネスの課題は時に複雑すぎて、「正解」などないのかもしれない。この複雑で不確実で、正解がないかもしれない世界で、ビジネスパーソンは「意思決定」をして前進しなければならない。
意思決定は、M&Aや投資判断などの大きなものに限らず、人脈の広げ方、他部署との横断型プロジェクトの進め方、顧客とのコミュニケーションにおいて顧客体験をいかに高度化するのか、新規事業開発をどのように進めるか、会社を辞めるか辞めないか、そしてイノベーション創出に向けた取り組み方に至るまで、我々は常に意思決定をしている。「正解のない中で意思決定をして前進する」のが、これからのビジネスパーソンにとって最大の課題であり、したがってより良い意思決定をするためには、人は永久に考え続けなければならない。
そのような状況下において経営理論は、ビジネスパーソンの考えを深め、広げる「思考の軸」となるために存在している。なぜなら理論とは、複雑なビジネスや組織のメカニズムに、正解というわけではないが、ある特定の人間の行動を前提にして「なぜそうなるのか(why)」という、一つの「切り口」、すなわち説明を与えてくれるからだ。理論とは、まるで複雑な事象をある角度から切り取る、鋭利なナイフのようだ。
結果、経営理論の切り口があれば、複雑なビジネス課題を一つの角度から鋭く説明することができ、whyに応えることができる。それは課題・事象をある角度から切ったものだから、事象全体の正解そのものではない。しかし、切り口がなければ思考は深まらない。経営理論という切り口があれば、それを軸にして自身の思考を深め、広げ、あるいは他者と同じ軸を使うことで議論を深く共有することができる。
そして経営理論によって説明が与えられ、人が納得すれば、それは人の「行動変容」を促す。反対に人は納得しなければ、行動しない。
経営理論は机上のためだけでなく、行動のためにある
現在、経済産業省のガイドラインを筆頭に新たな社会的な要請が次々と示されている。「ダイバーシティ&インクルージョン」「サステナビリティ」「イノベーション」「コープレートガバナンス」などは、その代表的な社会的な要請だ。多くの企業では、それらの要請に応えるべく変革を試みようとしている。しかしながら、これらの要請に対して、「何故それに取り組む必要があるのか」が納得しないままになっている企業は多い。「そういう潮流があるから」「経営者が命令したから」「他社がやっているから」と言われても、人は納得しない。経営者の中には、ご自身が進めたい会社の戦略が部下になかなか理解されない経験をお持ちの方も多いだろう。それは、自身の深い考えが経験知から来るものなので、充分に言語化、視覚化されていないからだ。
もし、そこに経営理論があれば、それは「その取り組みをなぜ進めなければならないのか」「なぜこの方針が重要なのか」のWhyに、一つの切れ味の良い説明を与える。結果として、人に説明がしやすくなり、彼らを納得させ、行動変容が生み出される。経営理論は、もはや机上のためだけにあるのではない。むしろ行動のためにあると言っていい。






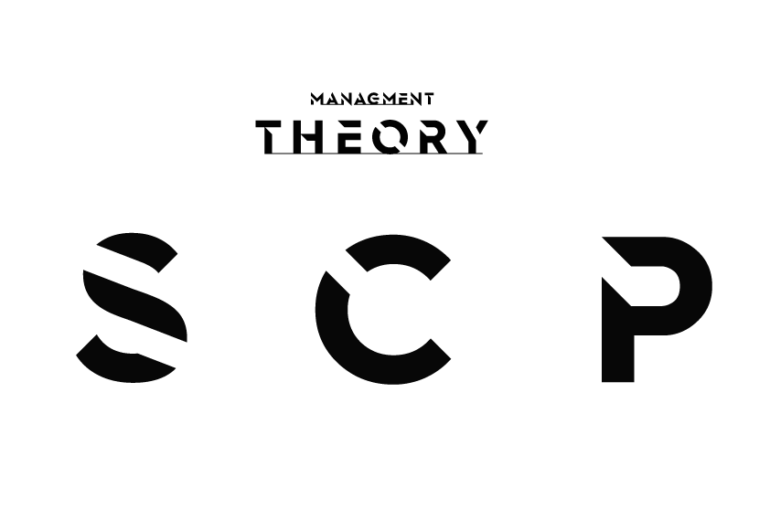



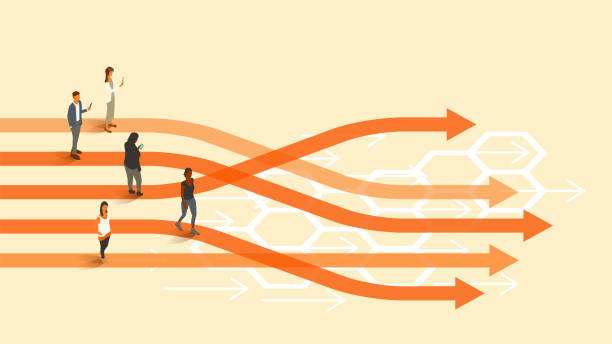


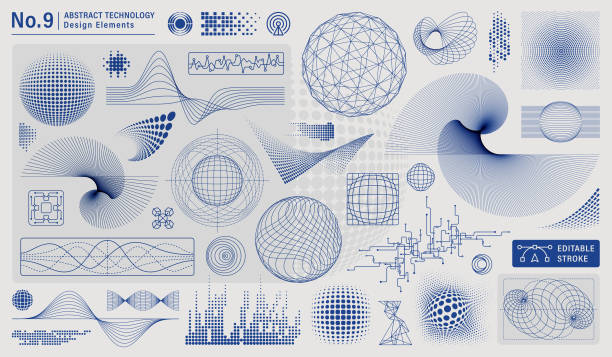








コメント