儲からない市場、儲かる市場
「投資の神様」といわれるウォーレン・バフェット氏が来日し、5大総合商社株の保有比率引き上げを公言したのは2023年4月。5大商社の時価総額合計は、大きく膨れ上がっている。彼は大きな安全域のなかで、「企業の内在的な価値」と、市場価格の差を利用して利益を得るという考え方をしているという。安定して収益性が高い(すなわち構造的に儲かる)業界において、自社の競争環境をなるべく完全競争から引き離し、独占に近づけるための手を打っている企業に投資をしている、もしくは5大総合商社のように、市場に存在する主要企業に投資するという投資戦略と言える。わたしはこの投資戦略の根底にあるのはSCP理論だと捉えている。
産業ごとに収益性に大きな差があることがわかる。例えば米国で同期間にROEが最も高かったのは製薬業、次いで食品産業、医薬品・医療機器である。他方で航空産業に至ってはマイナス34.8%と驚くべき数値となった。これは重要な示唆を与えてくれる。それは「この世には儲かる市場と、儲からない市場がある」という厳然たる事実。そしてSCPが第1に教えてくれるのは、その理由である。
その業界は儲かる構造になっているか
実際のビジネスで「業界が今後儲かるか、儲からないか」を見通すには、まず需要動向を分析することが多いのではないだろうか。ビジネスにおいて需要予測は当然重要だ。しかし「市場の成長性が高いから、企業の利益率も高い」とは限らない。例えば、2000年前後の米国半導体や情報通信産業の利益率は低く、逆に食品産業の利益率は高かった。しかし、前者と比べれば後者の市場成長率は鈍かったはずだ。産業の収益性は、需要の伸びだけでは説明できないのだ。むしろ重要なのは、「その産業がそもそも儲かる構造になっているかどうか」なのである。そのメカニズムを体系化したのが、SCPである。
企業の超過利潤がゼロになる
SCPは経済学を基盤しているため、経営学の基礎からアプローチしてことが近道だ。まず、経済学の「完全競争(perfect competition)」 という概念を理解してほしい。完全競争は以下の5つを条件とする市場の状態を考えてみよう。
条件1:市場に無数の企業が存在し、どの企業も市場価格に影響が与えられない
条件2:その市場に他企業が参入する際の障壁がない。その市場から撤退する障壁もない。
条件3:企業の提供する製品・サービスが同業他社と同質である。すなわち差別化されていない。
条件4:製品・サービスをつくるための経営資源が他の企業にコストなく移動できる。
条件5:ある製品・サービスの完全な情報を顧客、同業他社が持っている。
こんな市場はあり得ないと感じたかもしれないが、それだからこそ論理のベンチマークとなる。条件1~3に議論を絞り、この3つの条件から導かれる完全競争の重要な帰結は「企業の超過利潤がゼロになる」ということだ。「超過利潤」というのは企業が事業を続けられるギリギリの儲けを上回る部分」のことである。すなわち、超過利潤ゼロとは「ギリギリやっていけるだけの利益しか上げられていない」状態だ。
完全競争メカニズム
ある市場の企業が超過利潤を上げていると、その超過利潤を求めて他業界の企業やスタートアップが参入してくる。条件2のように参入コストがかからないのだから参入企業にとっては合理的な判断だ。しかし、条件3のように多くの企業が参入しても同じ製品をつくっていると各企業は製品特性で勝負できないのでライバル社に勝つために価格を下げるしかない。しかも条件1のように市場価格をコントールすることもできない。結果として完全競争下では「市場内のすべての企業がギリギリでやっていけるだけの利益しか上げられない」水準まで市場価格が下がっていく。
完全競争の対極にある「独占」
そしてこの完全競争の条件1・2・3の正反対を満たすのが「完全独占」である。すなわち、業界に1社だけ存在して価格をコントロールし、企業が参入できない状態である。1社しかいなければ差別化という概念も存在しない。
ミクロ経済学の消費者の「需要曲線」は、市場価格が下がるほど消費者の需要は増えるから、その関係は右下がりになる。線Sは企業の限界費用曲線と呼ばれるもの。
まず完全競争の場合、企業は市場価格に影響を及ぼせないので(条件1)、市場の価格メカニズムが完全に働き、最終的に市場の供給量(生産量)と需要量は Qa で一致する。したがって点Aが実現し、市場価格はPaとなる。これはよく知られた「需要と供給の一致の法則」で、この場合、企業の超過利潤はゼロとなる。
一方、完全独占の場合、状況はまったく異なる。独占企業は生産量も市場価格も自分でコントロールできる。したがって、独占企業が合理的なら、自社の超過利潤を最大にする生産量と価格を設定するはずだ。そして、その生産量は「限界費用」と「限界収入」が一致する点Bに対応するQbとなる。直感的に「合理的な企業は、『収入と費用の差(利潤)』が最大になるところで生産する」と考えていただければよい。
さて、独占企業にとって最適な生産量がQbだとしても、この企業は価格を供給曲線上のPbに設定する必要はない。なぜなら、独占企業は自社製品の価格を自在にコントロールできるからだ。したがって独占企業が合理的な場合、設定する価格はPcになる。なぜなら需要曲線が示すように、消費者は供給量がQbなら、Pcまでの価格を受け入れてくれるからだ。
このように完全独占の場合は、完全競争と比べて(1)供給量・需要量が減り(Qa→Qb)、(2)市場価格が上昇する(Pa→Pc)。買える量が減って価格が上がるのだから、消費者には望ましくない事態だ。他方で、(3)独占企業は大幅な超過利潤を得ることができる。台形ECBFを生産者余剰というが、これが最大になっている。独占の場合、企業は超過利潤を最大化できるのだ。
この「完全独占による市場支配力の行使」は、多くの国の競争法(独占禁止法)で違反となっている。したがって、これととまったく同じ状況が起きることは、ほとんどない。とはいえ「独占に近い産業」が現実に存在するのも事実だ。例えば、パソコンのオペレーティング・システム(OS)業界は米マイクロソフトが一時期独占に近い状況にあったために、それが消費者の不利益につながるとして、米国連邦地裁からOS部門とアプリケーション部門の分割を命令されたことがある。日本の企業ではYKKがジッパーの市場シェアを90%以上獲得したのは有名な話だ。しかし、儲からない業界である製造業の中での話なので高い利益率にはなっていない。儲からない業界で寡占した企業の典型だ。
米国内線航空業界は、多くの他業界と比べれば完全競争に近い。他方でパソコンのOS業界は完全独占に近い。皆さんの業界も、この完全競争と完全独占の間のどこかに必ず存在する。ポイントは「程度としてどちらに近いか」である。
ここまで来れば、完全競争を理解する重要性が理解できたのではないか。SCPの骨子とは、「完全競争から離れている業界ほど(すなわち独占に近い業界ほど)、安定して収益性が高い(すなわち構造的に儲かる)業界である」ということなのだ。あるいは「企業にとって重要なのは、自社の競争環境をなるべく完全競争から引き離し、独占に近づけるための手を打つこと」ともいってよい。
寡占はなぜ儲かるのか
SCP理論の前提を踏まえて、さらなる解説をする。重要な人物にカリフォルニア大学バークレー校教授のベイン、ハーバード大学教授のケイブス、そしてポーターがいる。この3人は言わば師弟のような関係にあったようで、ケイブスはハーバード大学で博士号を取得した後、学者としてのキャリアをUCバークレーでスタートさせ、そこで当時「経済学のSCP」を発展させていたベインと共同研究を行っている。その後ハーバードに戻ったケイブスの薫陶を受けたのが、ポーターだった。
まず、ベインによる「経済学のSCP」から始めよう。これまで述べたように、「ある産業が完全競争から離れるほど企業の収益率は高まる」というのがSCPの根本だ。「独占に近い」とは、少数の企業に売上げが集中しているということである。これは「寡占」と呼ばれる状況だ。「寡占は独占と違い、少数でもライバル企業が同じ産業にいるのだから、複数社で競争すれば各企業の収益性は低下するのではないか」と考える方もいるだろう。たしかにその可能性はあるのだが、それに対してベインは、「寡占産業では企業数が少ないので、1社の行動が他社の行動に影響を及ぼしやすい」という点に注目する。例えば、A、B、Cの3社だけが市場を占有している産業で、A社が製品価格を大幅に引き下げたら、B社とC社も対抗するために価格を引き下げるのが一つの「合理的な判断」になる。するとA社はB社・C社に対抗するため追加で価格を下げるだろう。そして、それはB社・C社のさらなる値下げにつながる。この状況が進みすぎると、業界は「極度の価格競争」に陥ってしまう。
逆に言えば、この状況を見通したA社が十分に合理的なら、「価格を引き下げない方が賢明」と判断するはずだ。B社とC社も同様だ。結果として、合理的なA社、B社、C社とも価格を引き下げないので、業界は価格競争に陥らず安定した収益を保つことができる(小さい企業が無数に存在する完全競争では、1社の行動が他社に影響を及ぼさないので、この状況は実現しない)。
もちろんこの行動は、競争法の範囲内で行われなければならない。しかし、この「暗黙の共謀」(tacit collusion)で特徴づけられる業界は現実に多くある。食品関係業界はその特徴が顕著かもしれない。例えば大手4社の寡占状況にある日本のビール業界では長年大幅な値下げ競争が起きず、結果的に各社の収益性は比較的安定していた。米国のシリアル業界も同様だ。コーラ業界はペプシとコカ・コーラの2強が、互いに価格競争を仕掛けないことで高い収益性を保っている。この仮説を実証して「経済学のSCP」を切り開いたのが、ベインが51年に経済学の学術誌『クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス』(QJE)に発表した論文だ。この研究では36年から40年の米国42産業のデータを使い、寡占度が高い市場ほど、企業の平均利益率が高くなる傾向が示されている。
SCP理論を踏まえて、さらなる解説に入ろう。ここで覚えていただきたい名前が、カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)教授のジョー・ベイン、ハーバード大学教授のリチャード・ケイブス、そしてマイケル・ポーターである。余談だが、この3人は言わば師弟のような関係にある。ケイブスはハーバード大学でPh.D.(博士)を取得した後、学者としてのキャリアをUCバークレーでスタートさせ、そこで当時「経済学のSCP」を発展させていたベインと共同研究を行っている。その後ハーバードに戻ったケイブスの薫陶を受けたのが、ポーターだった。
まず、ベインによる「経済学のSCP」から始めよう。これまで述べたように、「ある産業が完全競争から離れるほど(独占に近づくほど)企業の収益率は高まる」というのがSCPの根本だ。「独占に近い」とは、少数の企業に売上げが集中しているということである。これは「寡占」と呼ばれる状況だ。「寡占は独占と違い、少数でもライバル企業が同じ産業にいるのだから、複数社で競争すれば各企業の収益性は低下するのではないか」と考える方もいるだろう。たしかにその可能性はあるのだが、それに対してベインは、「寡占産業では企業数が少ないので、1社の行動が他社の行動に影響を及ぼしやすい」という点に注目する。例えば、A、B、Cの3社だけが市場を占有している産業で、A社が製品価格を大幅に引き下げたら、B社とC社も対抗するために価格を引き下げるのが一つの「合理的な判断」になる。するとA社はB社・C社に対抗するため追加で価格を下げるだろう。そして、それはB社・C社のさらなる値下げにつながる。この状況が進みすぎると、業界は「極度の価格競争」に陥ってしまう。
逆に言えば、この状況を見通したA社が十分に合理的なら、「価格を引き下げない方が賢明」と判断するはずだ。B社とC社も同様だ。結果として、合理的なA社、B社、C社とも価格を引き下げないので、業界は価格競争に陥らず安定した収益を保つことができる(小さい企業が無数に存在する完全競争では、1社の行動が他社に影響を及ぼさないので、この状況は実現しない)。もちろんこの行動は、競争法の範囲内で行われなければならない。しかし、この「暗黙の共謀」(tacit collusion)で特徴づけられる業界は現実に多くある。食品関係業界はその特徴が顕著かもしれない。例えば大手4社の寡占状況にある日本のビール業界では長年大幅な値下げ競争が起きず、結果的に各社の収益性は比較的安定していた。米国のシリアル業界も同様だ。コーラ業界はペプシとコカ・コーラの2強が、互いに価格競争を仕掛けないことで高い収益性を保っている。
この仮説を実証して「経済学のSCP」を切り開いたのが、ベインが51年に経済学の学術誌『クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス』(QJE)に発表した論文だ(※2)。この研究では36年から40年の米国42産業のデータを使い、寡占度が高い市場ほど、企業の平均利益率が高くなる傾向が示されている。
ベインの参入障壁の視点
では、どのような業界が寡占になりやすいのだろうか。様々な要因があるが、なかでもベインが注目したのが、先ほどの条件2の逆、すなわち「参入障壁」である。業界に参入する障壁(コスト)が高ければ、既存企業は超過利潤を占有できる(※3)。参入障壁には、規制など制度的なものも含まれる。例えば、日本では銀行などの認可事業は安定して収益性が高くなりがちだ。そして、この制度要因に加えてSCPで重視されるのが、「規模の経済」(economies of scale)いわゆる「スケールメリット」だ。
規模の経済で特徴づけられる産業は、生産量が増えるほど平均費用が下がる。この業界では、つくればつくるほどコスト競争力が増すので、大規模企業ほど超過利潤を得やすい。すると、それを求めて、他業界の企業やスタートアップ企業がこの産業への参入を検討するはずだ。しかし、この産業で既存企業と競争するには、同じ低水準の平均費用を実現する大規模生産をいっきに達成しなければならない。それは大きな費用・リスクを伴うから、合理的な他企業やスタートアップ企業はなかなか参入に踏み切れない。したがって、規模の経済が強く働く産業は、実質的に参入障壁が高く、独占・寡占に近づくのである。
例えば大規模な固定費が必要な業界では、この効果が顕著なことが知られている。固定費が大きい場合、生産量を大幅に増やさないと平均費用が十分に下がらないからだ。したがって石油化学などの装置産業は、一般に参入障壁が高い。新薬一つつくるのに平均200億円のR&D費用が必要とされる製薬業も、参入は難しい。米国の製薬業は利益率が安定して高いが、それにはこの構造的背景がある。
このように経済学のSCPは、完全競争の条件2(=参入コストがゼロ)の「逆条件」に着目している。参入障壁が高い業界ほど(=条件2の逆)、既存企業が価格支配力を持てるので(=条件1の逆)、安定して超過利潤を得られるのだ。
ケイブスとポーターの「企業グループ」の視点
ベインがQJEに論文を発表してから26年後の1977年、ケイブスとポーターが同じQJEに共同論文を発表した(※4)。そしてこの論文こそが、それまで経済学で探究されてきたSCPを「経営学のSCP」に昇華させる契機となった。「ポーターの競争戦略」の幕開けとなった論文ともいえる。実際、いまでも欧米の経営学博士課程でこの論文が読まれることは多い。
ケイブスとポーターは「ベインが主張してきた『業界の参入障壁』だけでは企業の収益率を説明するには不十分」と主張した。代わって彼らが提示したのは、「そもそも参入障壁は産業だけにあるのではない。一産業のなかにも『企業間の移動障壁』がある。それを理解しないと本質を見誤る」というものだった。ケイブスとポーターによると、業界内の「移動障壁」は企業それぞれの特性によって規定される。すなわち同じ業界のなかでも、製品ラインアップ・進出地域・費用構造などで似ている企業と似ていない企業があり、似た企業同士を一つの「グループ」と考えると、同じ産業でも特性の異なる企業グループが複数存在することになる。そしてあるグループの企業が、特性の違う別グループに参入するのは難しい(移動障壁が高い)。
日本の国内自動車製造業を取り上げよう。この業界にも、企業同士のグループは存在する。例えば「軽自動車メーカー」と「乗用車メーカー」は別のグループだろう。両グループの間の移動障壁も高そうだ。カルロス・ゴーン氏がCEOに就任する前の日産自動車は軽自動車に進出していなかったし、他方で国内販売の9割以上を軽自動車が占めるスズキは、乗用車セグメントに長らく本格参入してこなかった。BMWやダイムラー(メルセデス・ベンツ)などの「ラグジュアリー車メーカー」と「大衆車メーカー」も違うグループだろう。
このように「『産業』というのはあくまで制度的に定義されたもので、その参入障壁を考えるだけでは企業の収益性は説明できない」というのが、ケイブスとポーターの主張だ。同じ産業にも企業特性ごとにグループがあり、企業収益にとってより本質的なのはそのグループ間の移動障壁だ、ということなのである。
「ポーターの競争戦略」の起源
さて、そうだとすれば、高い超過利潤を得たい企業に重要な戦略は、「自社のグループの特性を、なるべく他グループと似せない」ことになる。さらに言えば、「自社のグループの企業数は少ない方が、そのグループが独占状況に近づくから超過利潤が高まる」ともいえる。これこそが「経営学のSCP」の重要なポイント、すなわち、「差別化戦略の重視」につながるのだ。「似せないこと」は「差別化すること」と同義だ。ポーターの競争戦略では差別化戦略が常に重視されるが、その源流はここにあるのだ。
そして、これは完全競争の条件3(企業の同質性)の真逆でもある。よくビジネスでも差別化戦略は議論される。実際多くの企業が、技術、機能、デザイン、ブランドなど様々な手段で差別化に成功している。現代なら例えば、アップル、スターバックス、良品計画、コマツ、ファナックなどがその代表だろう。SCPからみれば、それは可能な限り自社の周囲の競争環境(グループ)を完全競争から遠ざけて、独占に近づけていることにほかならないのだ。
このように、まずベインを中心とする経済学のSCPは、儲かる競争環境の仕組みを「産業の高い参入障壁(条件2の逆)→少数企業による産業支配(条件1の逆)」というロジックに求めた。これに対してケイブスとポーターは、「企業レベルでの戦略的な差別化(条件3の逆)→企業グループ間の高い移動障壁(条件2の逆)→少数の企業がグループを支配(条件1の逆)」というロジックを提示したのだ。
ベインによる経済学のSCPも、ポーター式のSCPも、根底にあるのは「いかにして競争環境を完全競争から乖離させるか」であることに変わりはない。違いは、その出発点をどこに置くか、ということなのだ。経済学のSCPが産業構造を中心に考えていたのに対し、それを企業グループレベルまで解き放ち、だからこそ「差別化戦略のような企業の競争戦略が重要」という地平を切り開いたのが、ポーターによる経営学のSCPなのである。経営学においてポーターの競争戦略は、競争戦略論という新しい分野を切り開いた一大革命であり、それは彼の著書や様々な経営本を通じて多くのビジネスパーソンに伝わった。その源流はここまで解説したSCP理論であり、その端緒となった彼らの1977年のQJE論文にあるのだ。
さて、このポーターとケイブスのQJE論文が発表されてから、すでに45年以上が経過している。では、このSCPの基本主張は21世紀の現代では色あせたものになってしまっているのだろうか。ここからは私見になるが、筆者はそうは考えない。むしろ、SCPの基礎メカニズムを理解しておくことの重要性は、現在の方がはるかに高まっているのではないだろうか。例えばそれは、現在世界で隆盛を極めるプラットフォームビジネスのメカニズムが、まさにSCPの主張と整合的だからだ。この点に触れておこう。
プラットフォーマーが生み出す、新時代の「独占」
現代のインターネット社会で隆盛を極めているのが、プラットフォーマー企業であることは論を待たないだろう。いわゆるGAFAと呼ばれるグーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルといった世界の時価総額ランキングの上位を占める企業はいずれもプラットフォーマーだし、それに続くウーバーやエアビーアンドビーもそうである。中国のアリババ、テンセントもしかりだ。そしてこれらプラットフォーマー企業が圧倒的に収益をあげられるメカニズムは、SCPと極めて整合的だ。なぜなら、各社とも、検索システム、EC、SNS、メッセンジャーアプリなどそれぞれの分野で、独占的な地位を得ているからだ。独占に近いからこそ収益性が高い(あるいは「高くなる」と投資家が評価している)のだ。
フェイスブックのネットワーク効果
フェイスブックを例に取ろう。同社がなぜSNSで独占に近い状況を築けているかといえば、その背景にある「ネットワーク効果」(network effect)を理解することが重要だ。ネットワーク効果とは、「ユーザーにとって、他の多くの人が同じ製品・サービスを使うほど、自身もそれを使う効用が高まる」特性のことだ。我々がなぜフェイスブックを使うかといえば、その最大の理由は「他の多くの人が使っているから」にほかならない。いかにフェイスブックのユーザー体験やインターフェイスが優れていても(差別化ができていても)、そこに自分の友人や知り合いが多く参加していなければ、使う意味がない。
逆に言えば、ひとたび一定数がフェイスブックを使い出すと、「みんなが使っているから」と言うだけの理由で、さらに多くの人がフェイスブックを使い始めるのだ。するとユーザーがさらに増えるので、そのさらに拡大したメリットを求めて、またさらに多くの人がフェイスブックに集まる、そして、またさらに多くの人が集まれば、そのメリットを求めてまたまたさらに多くの人が集まる……という雪だるま式のメカニズムが働くのだ。
結果としてSNSでは、ティッピング・ポイントを超えて利用者数が増えだすと、参加者数が自然に増え続け、やがてほぼ独占状況に至る。そしていったんこの独占状況を実現すると、それは簡単には揺るがない。結果、そのプラットフォーマー企業が超過利潤を獲得し続けるのだ。
「プラットフォーム型ビジネス」が一人勝ちするワケ
ネットワーク効果の要素は、グーグルにも、アリババにも、テンセントにも、マイクロソフトのビジネスにもある。インターネットが圧倒的に普及し、世界中の人々がつながるようになった世界で「プラットフォーム型ビジネス」が一人勝ちの状況をつくりやすい背景は、実はこのメカニズムがあるからなのだ。マイクロソフトも長い間ウィンドウズがパソコンのOS市場を独占しているが、これもそれが理由だ。アマゾンやアリババがECプラットフォームで圧倒的に強いのもそうだ。そしてこのネットワーク効果の帰結は、「独占に近づく方が望ましい」というSCPと整合する。ただし、ポーターケイブスの主張との違いは、ティッピング・ポイントを超えた後は、差別化戦略ではなくこのネットワーク効果で独占に向かうことだ。
逆に言えば、ネットワーク効果で自然に独占を得ているフェイスブックにSNSで真っ向勝負してもなかなか勝ち目はない。したがってSCPを基準に考えるなら、同じSNSでもフェイスブックとは違うグループをつくり、そのグループ内で新しい独占状態をつくっていくのが望ましい、ということになるだろう。ティックトックや数年前に流行ったスナップチャット、フェイスブックに買収されてしまったが現在も人気の高いインスタグラムなどは、それを狙ったビジネスといえる。
SCPを思考の軸へ
このように、SCPのエッセンスはすべて「完全競争と完全独占のスペクトラム」に集約されている。自社の周りの競争環境を少しでも独占に近づけた企業が安定して高い超過利潤をあげられる、ということなのだ。差別化やネットワーク効果はその手段にすぎない。SCPの説明力と重要性は、時代を超えてなおも高いのだ。「ポーターの戦略」の名は、これほど知られているにもかかわらず、「なぜ(Why)差別化戦略が重要なのか」「なぜ業界構造分析が重要なのか」などには、納得できる説明がなされないことが多い。これらの主張の背景には、すべてSCPがあるのだ。当コンテンツを通じて、理論としてのSCPを皆さんの思考の軸としていただきたい。
なぜ日本でプラットフォーマーが誕生しないのか
日本の経済成長は製造業によってなされたといってもいいほど、日本の製造業が成長した時代があった。もちろん「規模の経済」の原理に支えられた結果だ。しかし、日本の製造業の経営者は「自社のグループの特性を、なるべく他グループと似せない」ことに失敗した。さらに言えば、「自社のグループの企業数は少ない方が、そのグループが独占状況に近づくから超過利潤が高まる」という状態を達成しなかった。これは「経営学のSCP」の重要なポイント、すなわち、「差別化戦略」を実行しなかったことを意味している。そして、最も影響力と経営資本を持っていた日本製造業がこの階段を踏み外したことが「失われた30年」を生み出し、現在のイノベーション後進国と呼ばれる所以となった。であるならば、プラットフォーム型ビジネスを日本製造業がおこなったら、どこに可能性が残されているのではなかろうか。これが私たちが取り組んだプロジェクト「製造業におけるデジタルプラットフォーム戦略」であった。しかし、とある製造業のトップマネジメントはネットワーク効果の「ユーザーにとって、他の多くの人が同じ製品・サービスを使うほど、自身もそれを使う効用が高まる」という特性を理解せず、そこに投資をしなかった。非常に残念だが、投資判断が行われない場合、いかなる優れた戦略も意味をなさない。その戦略はそのままスタートアップが実行して大きな収益を生む結果となった。スタートアップの経営者の身近にはプラットフォームがあり、そこにネットワーク効果という特性があることを感覚的に理解していたと想像する。製造業のトップマネジメントの交代を促進しなければ、日本経済が減退するという意見が後をたたないのは、このような悲劇が繰り返されているからに他ならない。要するにSCPを思考の軸にしない企業は衰退を強いられる。そこに自分の人生を委ねている従業員は露頭に迷うことになる。日本の企業の経営リテラシーの低さはSCP理論への理解の低さと言い換えても差し支えない。

















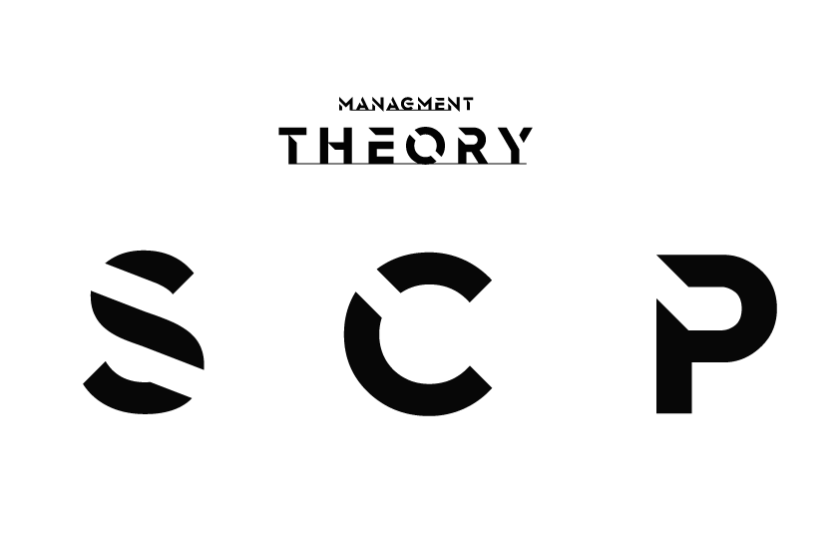





コメント