素晴らしいパートナーと「攻め」の契約を結び、ついにプロジェクトが始動する。まずは「PoC(Proof of Concept:概念実証)」からだ。しかし、多くのオープンイノベーション(OI)が、このPoCを終えたまま次のステップに進めず、立ち消えになってしまう。
いわゆる**「PoC死」**です。なぜ、実証実験は「成功」したはずなのに、事業化(スケールアップ)の谷を越えられないのか。ガイドブックが示す「正しいプロセス」の裏に潜む、運営の真実をJOIA(日本オープンイノベーション協会)の実績から解き明かします。
【教科書の解説】:「プロジェクト運営」のプロセス
まず、ガイドブックが示す「プロジェクト運営」の王道プロセスを見てみましょう。 一般的に、OIプロジェクトは以下のステップで進められます。
- テーマ設定: 自社の課題や戦略に基づき、協業のテーマを明確にします。
- PoC(実証実験): 設定したテーマ(仮説)が技術的・商業的に成立するかを、パートナーと小さく検証します。
- スケールアップ: PoCで有効性が確認できたら、本格的な事業化フェーズへと移行します。
これは、リスクを最小限に抑えながらイノベーションを進めるための、非常に合理的で「正しい」プロセスです。
【JOIAの付加価値】:なぜ「正しいプロセス」がPoC死を招くのか
しかし、JOIAが分析する「PoC死」の現場では、この「正しいプロセス」を忠実に守った結果、失敗しているケースが後を絶ちません。教科書が触れない、本質的な論点は2つあります。
示唆1:「PoC死」の正体は「既存事業部との溝」
JOIAが分析する「PoC死」の最大の原因、それは技術やアイデアの問題ではなく、**「既存事業部との連携不足」**です。
OIの担当部署(例えば「イノベーション推進室」など)は、PoCの成功に全力を注ぎます。しかし、その成果をいざ事業化しようとした時、受け皿となる既存事業部(営業部、製造部、開発部など)からこう言われるのです。
「そんなニッチな市場、誰が売るんだ?」 「既存の製品ラインナップとカニバリズム(共食い)を起こす」 「ウチの品質基準を満たせるのか?」
OI担当と既存事業部との間には、ミッションもKPIも異なる**「深い溝」**が存在します。この溝をPoCの「後」ではなく、プロジェクトの「最初」からどう埋めるか。JOIAは、この「社内政治」こそがプロジェクト運営の核心だと考えています。
示唆2:「成功」より重要な「賢明な撤退」の基準
もう一つの問題は、ガイドブックが「成功(=スケールアップ)」への道筋を示しがちだという点です。
しかし、実践の場では、**「賢明な撤退(Wise Withdrawal)」**の基準を持つことこそが重要です。すべてのPoCが事業化すべきではありません。PoCとは「検証」ですから、「この道は間違いだった」と早く安く知ることもまた、大きな「成果」なのです。
多くの企業が、この「撤退基準」を曖昧にしたままPoCを始めてしまいます。 その結果、「せっかくここまでやったのだから」と、成果の出ないプロジェクトにリソースを浪費し続けます。JOIAが定義する「良い失敗」とは、「学び」を最大化し、次の挑戦にリソースを振り向けるための「明確な撤退」を指します。
結論
プロジェクト運営とは、ガイドブック通りのプロセスをなぞることではありません。 それは、「社内の溝」という政治に向き合い、「賢明な撤退」という決断を行う、生々しい実践の場です。
PoCを始める前に、「誰を巻き込むべきか」「いつ辞めるべきか」を設計できているか。 その覚悟こそが、「PoC死」の谷を越える鍵となります。
次回は<結論>として、これら全てを包摂する「組織文化」について、JOIAの最終的なメッセージをお伝えします。


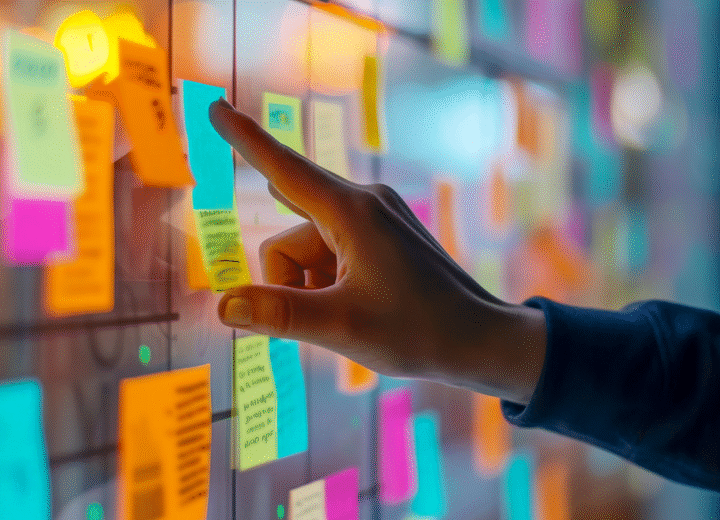

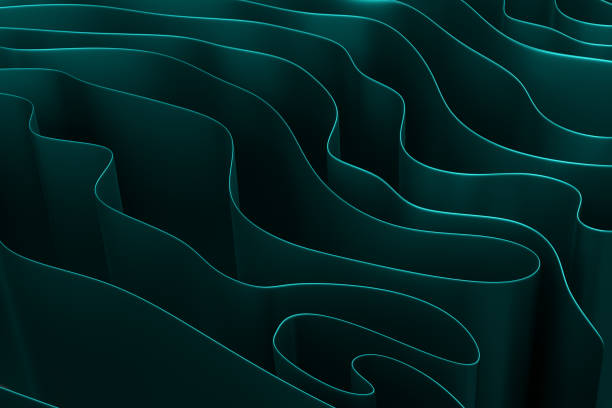
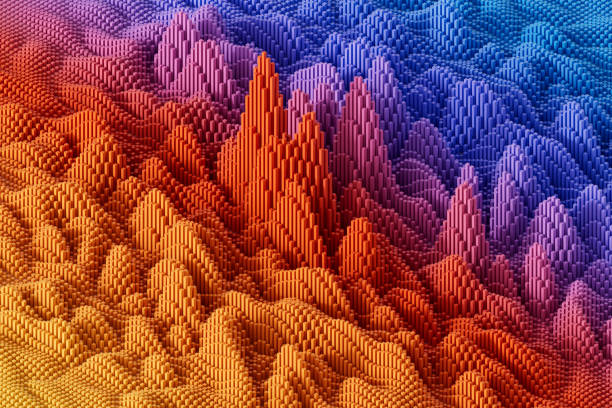


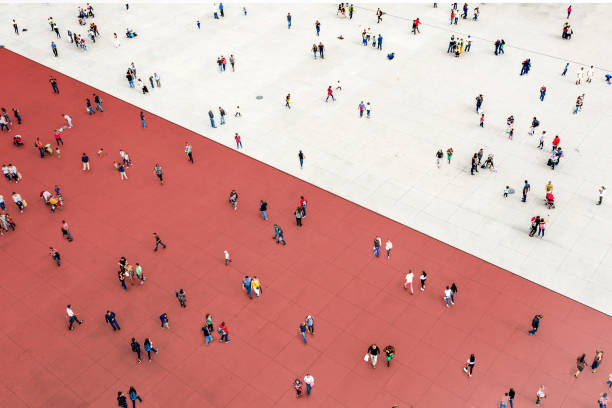






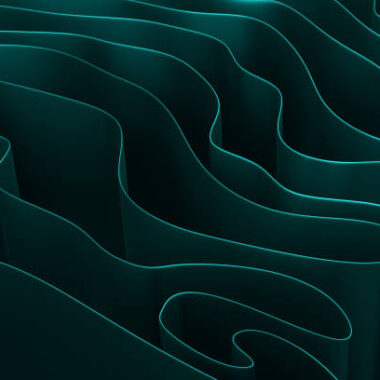


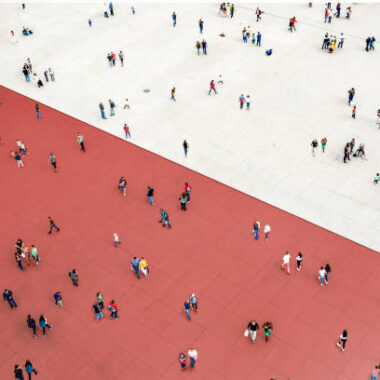




コメント