オープンイノベーション(OI)のパートナーが見つかり、いざ協業へ。しかし、多くのプロジェクトがここで「契約の壁」にぶつかり、停滞します。NDA(秘密保持契約)の締結に数ヶ月、共同開発契約は難航……。なぜでしょう?
それは、多くの企業が契約と知財を「守り」のツールとしか見ていないからです。ガイドブックが教える「守り方」の先にある、「攻め」のルール設計について、JOIA(日本オープンイノベーション協会)の実践知から解説します。
【教科書の解説】:「契約」と「知財」の重要性
まず、ガイドブックが示す「契約・知財」の基本を押さえましょう。 教科書は、イノベーションの成果(=果実)を守るために、「契約の重要性」と「知財の守り方」を解説します。
- NDA(秘密保持契約): 議論の前提として、自社の機密情報を守るために不可欠。
- 共同開発契約: 協業によって生まれた成果物(知財)の権利帰属を明確にし、将来の紛争を未然に防ぐ。
これらは、自社の権利と財産を守る「防衛」の観点から、法務・知財部門が整備した雛形(テンプレート)を用いることが推奨されます。確かに、これは法務実務における一つの「正解」です。
【JOIAの付加価値】:スピードを生む「攻め」のルール設計
しかし、JOIAが目撃してきたOIの現場では、この「正解」が協業の最大の足かせになるケースが後を絶ちません。教科書が触れない、実践的な論点は2つあります。
示唆1:最大の壁は「自社の法務・知財部」
驚くかもしれませんが、協業のスピードを阻む最大の障壁は、パートナー企業ではなく「自社の法務・知財部」であるケースが圧倒的に多いのです。
彼らのミッションは「会社のリスクを最小化すること」。そのため、ガイドブック通りの完璧な契約書(=自社に有利で、リスクがゼロに近い契約書)を目指します。
「そのスタートアップは信用できるのか?」 「万が一、情報漏洩したら?」 「知財の持ち分は、1%でも多く確保せよ」
こうした「リスク管理者」としての鉄壁の姿勢が、パートナー企業との信頼関係構築を妨げ、貴重な時間を奪います。JOIAが重視するのは、法務・知財部をいかに「リスク管理者」から「事業推進パートナー」に変えるか、という組織内部の変革です。
示唆2:完璧な契約が「PoC死」を招く
論点1とも関連しますが、教科書通りの「完璧な契約」を目指すあまり、協業の「スピード」を失っていませんか?
特に、まだ成功するかどうか分からない「まずは小さく試す(PoC)」の段階で、数年後の事業化フェーズを見越した重厚な知財の取り決めを議論するのは、典型的な失敗パターンです。
スタートアップの経営資源(ヒト・カネ・時間)は有限です。大企業側の法務部と数ヶ月にわたる契約交渉をしている間に、彼らの熱意は冷め、市場の好機(マーケットウィンドウ)は閉じてしまいます。
JOIAが推奨するのは、失敗と試行錯誤を許容する「アジャイルな契約形態」です。 例えば、「PoCフェーズ」と「事業化フェーズ」で契約を明確に分ける。「PoCでの成果(知財)は、一旦棚上げ(または共有)し、事業化が決まった時点であらためて協議する」といった、「共に走るため」のルール設計こそが実践では求められます。
結論
契約や知財は、自社を「守る」ためだけにあるのではありません。 それは、パートナーと「共に攻める」ための共通ルールです。
ガイドブックが示す「リスク回避」の視点だけでは、イノベーションのスピードは生まれません。「リスクを取って挑戦する」ために、法務部門をも巻き込んだ「攻め」のルールを設計できるか。
JOIAは、この「契約」の再定義こそがOI成功の鍵だと考えます。
次回は、こうして契約を結んだプロジェクトが、なぜ「PoC死」で終わってしまうのか、その「プロジェクト運営」の真実に迫ります。


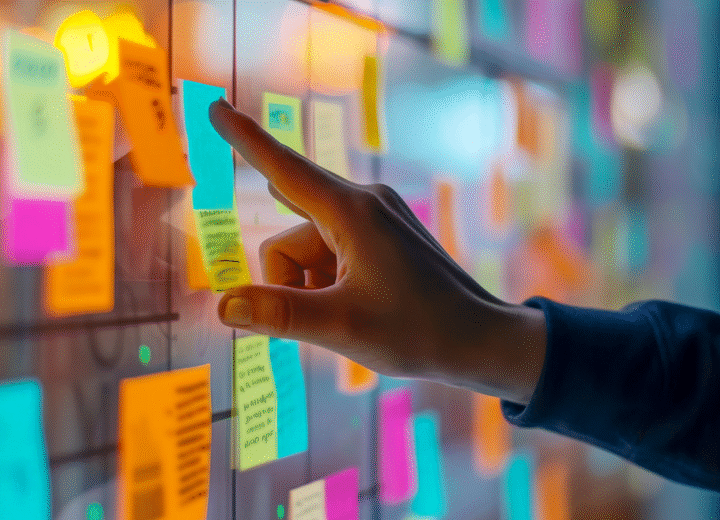



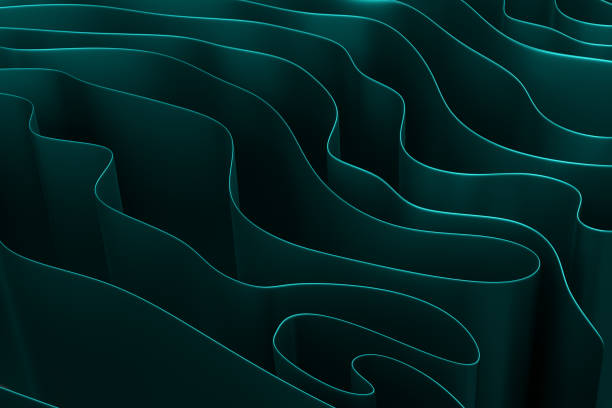
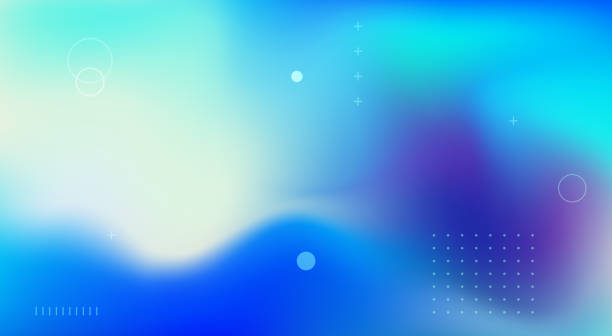






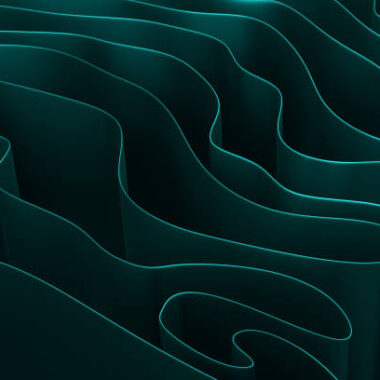








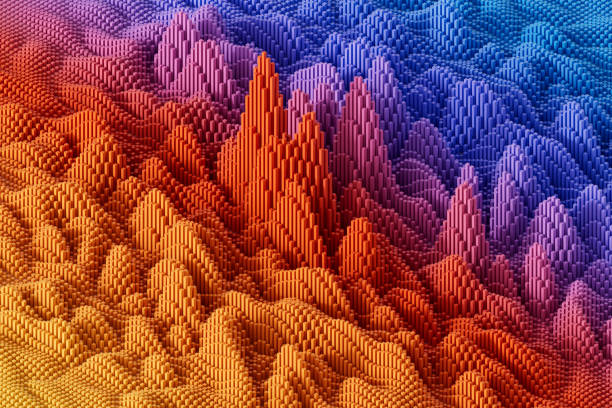


コメント