近年、オープンイノベーション(OI)の重要性が叫ばれ、『実務者のためのオープンイノベーションガイドブック』(日本オープンイノベーション研究会・著)のような優れた教科書も登場した。しかし、教科書通りに進めても、なぜ多くの取り組みは成果を出せずに終わるのか。JOIAの豊富な実践知から、ガイドブックが示す「基礎知識」の”次”にある、本質的な論点を解説する。
【教科書の解説】OIの「基礎知識」とは何か
まず、ガイドブックが示す「基礎知識」のポイントを押さえましょう。 一般的に、OIの定義とは「自社だけでなく、外部の技術やアイデアを積極的に活用し、イノベーションを創出すること」です。
教科書が示す基本的なメリットは、主に以下の2点に集約されます。
- リソースの補完: 自社にない技術、アイデア、人材を外部から調達できる。
- スピードの向上: すべてを自前で開発するより、圧倒的に早く市場に到達できる。
これらは、OIの「型」として非常に正しい知識です。多くの企業が、このメリットに期待してOI推進室のような部署を設立します。 しかし、現実はどうでしょうか。
【JOIAの付加価値】教科書が触れない「2つの落とし穴」
JOIA(日本オープンイノベーション協会)は、その設立以来、数多くの企業のOIの現場に伴走してきました。その豊富な実績から断言できるのは、OIの失敗は「知識不足」で起きるのではない、ということです。
教科書通りの「型」を学んでも、多くの企業が陥る「2つの本質的な落とし穴」があります。
落とし穴1:OIが「目的化」する病
最も多い失敗がこれです。 経営陣から「我が社もOIを推進せよ」という号令がかかり、担当部署が設立される。担当者は、教科書通りに「ピッチイベントの開催」や「スタートアップとの面談件数」をKPI(重要業績評価指標)に設定します。
しかし、考えてみてください。 「何のために」協業するのか? 「自社のどの事業の、どんな課題を解決したいのか?」
この「目的」=「事業戦略上のWhy」が曖怠なまま、「OIをやること」自体が目的になっていないでしょうか。
ガイドブックは「どうやるか(How)」を教えてくれます。しかし、JOIAが現場で見る失敗の9割は、この「なぜやるのか(Why)」の欠如に起因しています。目的がなければ、どれだけ多くのスタートアップと会っても、それは単なる「流行り物集め」で終わってしまいます。
落とし穴2:「自前主義」という”深層心理”
教科書は「リソースの補完」と簡単に言いますが、現場はそれほど単純ではありません。 特に、歴史と技術力のある大企業ほど、根深い「自前主義のプライド」が存在します。
- 「外部の技術など、大したことはない」
- 「自社の技術こそが最高だ」(NIH症”Not Invented Here”症候群)
- 「外部に頼るなど、自分たちの無能を認めるようで抵抗がある」
こうした**”組織の深層心理”や“人の感情”**こそが、OIの最大の障壁です。
JOIAは、この「感情の壁」を乗り越えるプロセスこそがOIの本質だと考えています。外部のパートナーと対話することは、自社の「当たり前」を疑い、自社の「弱さ」を認めるプロセスに他なりません。 ガイドブックが示す「型」や「知識」だけでは、この最も厄介な「人の問題」は決して解決できないのです。
結論
OIの教科書を学ぶことは、スタートラインとして重要です。 しかし、それだけではイノベーションは起きません。
「なぜやるのか」という戦略的な「目的」と、「自前主義」という感情的な「壁」。 この2つの論点にどう向き合うか。それこそが、ガイドブックには書かれていない、OI実践の第一歩です。
次回は、多くの企業が陥る「パートナー探索」の落とし穴について、JOIAの実践知から解説します。


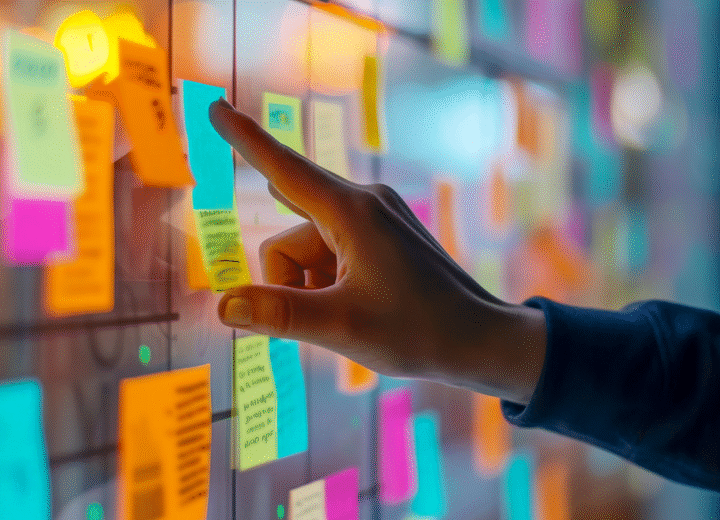
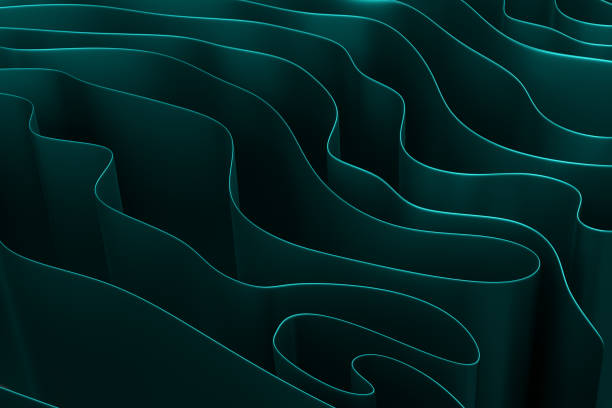



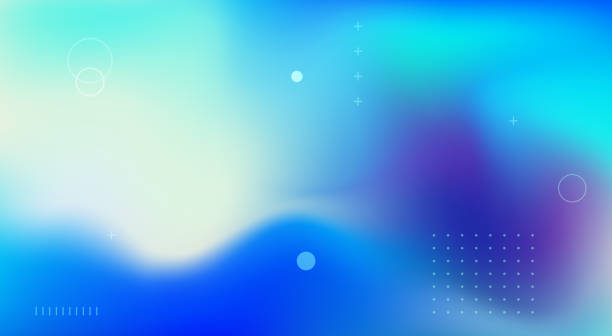

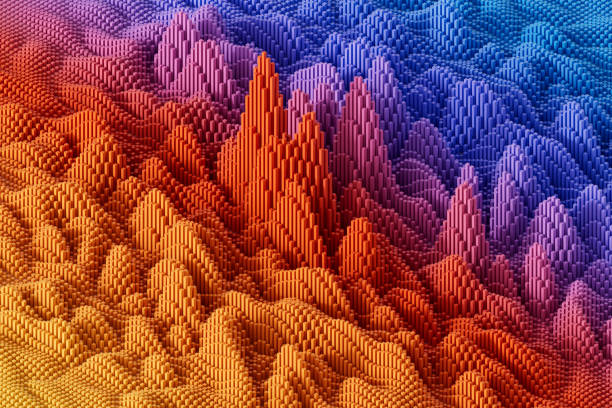




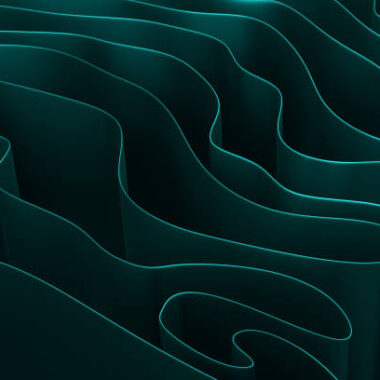

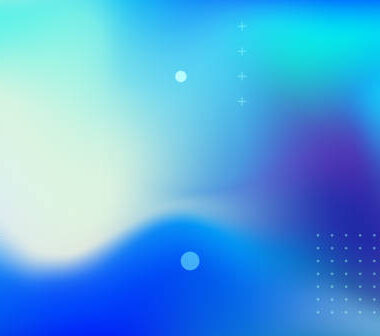






コメント