[寄稿] TMI総合法律事務所 パートナー弁護士(M&A・スタートアップ法務担当) 高橋 健氏
1. なぜ、法務部が「イノベーションの壁」と呼ばれるのか
日本オープンイノベーション協会(JOIA)の会員企業様から、私たちTMI総合法律事務所に寄せられるご相談で、最も多いものの一つがこの悩みです。
「事業開発部がスタートアップと進めようとした実証実験(PoC)が、法務部のレビューで半年も止まっている」
「NDA(秘密保持契約)の交渉だけで2ヶ月かかり、スタートアップから『御社とはスピード感が合わない』と見限られてしまった」
これは、法務部が無能なのでも、怠慢なのでもありません。多くの場合、法務部は「既存事業の巨大なリスク」から会社を守るために最適化されています。彼らにとって、スタートアップとの協業は「リスクの塊」に見えて当然なのです。
- リスク1(知財流出): こちらが開示する情報が、競合他社に漏れるのではないか。
- リスク2(知財帰属): 協業で生まれた成果物(知財)の権利を、全て持っていかれるのではないか。
- リスク3(法的責任): スタートアップのサービスが個人情報漏洩や事故を起こした場合、ブランドを持つ自社が全責任を負わされるのではないか。
これらのリスクを「ゼロ」にするために、従来の重厚長大な契約書を求め、交渉を長引かせた結果、イノベーションの「機会」という最大の果実を逃してしまう。
本稿では、この「法務のジレンマ」を乗り越え、法務・知財部門がイノベーションの「ブレーキ」から「アクセル」へと変わるための、最先端の契約実務について提言します。
2. 「NDA」で2ヶ月もかける愚—スピードを殺さない3つの実践知
協業の入り口であるNDA(秘密保持契約)で停滞するのは、致命的です。スタートアップの時間は限られています。
実践知1:目的を「秘密情報」から「人材」の評価に変える
そもそも、NDA締結前に「秘密情報」を交換しすぎるのが間違いです。 最初のミーティングの目的は、お互いの「人」と「カルチャー」が合うかを見極めることであるべきです。NDA締結前のディスカッションでは、「物流のこの部分に課題がある」という「課題の存在」までを開示し、「その課題の背景にある詳細な生データ」は開示しない、といった情報開示レベルの設計が重要です。
実践知2:「双方向」ではなく「片方向」のNDAを使い分ける
スタートアップと「まず話したい」段階では、スタートアップ側に開示させる秘密情報はほとんど無いはずです。 この場合、大企業側からスタートアップ側への**「片方向(One-way)」のNDA**(=大企業が開示する情報だけを守ってもらう)を提示すれば、スタートアップ側の法務レビューの負荷はほぼゼロになり、即日締結できるケースもあります。
実践知3:JOIA推奨の「標準NDA(アジャイル型)」を利用する
JOIAでは、TMI総合法律事務所の監修のもと、**オープンイノベーションに特化した「標準NDA」**のひな形を会員向けに提供しています。 これは、知財の帰属など、PoC段階で決めるべきでない重い論点をあえて排除し、「まずはPoCに進むための最低限の信頼関係を構築する」ことに特化したアジャイル型の契約書です。会員同士であれば、この標準NDAを利用することで、交渉時間を劇的に短縮できます。
3. 「PoC死」を防ぐ、知財の取り扱い
NDAの次に来る壁が、実証実験(PoC)のための「共同開発契約」です。ここで最も揉めるのが、**「成果物(知財)の帰属」**です。
大企業は「金も場所もデータも提供するのだから、成果物はすべて当社に帰属すべきだ」と考えがちです。 一方、スタートアップは「私たちのコア技術(バックグラウンドIP)がなければ、この成果物(フォアグラウンドIP)は生まれなかった。これが大企業に取られたら死活問題だ」と考えます。
この交渉がまとまらず、PoCが実行できない「PoC死」が多発しています。
解決策:「成果物」を2つに分けて考える
私たちは、「PoCの成果物」と「その先の事業化の成果物」を、あえて別の契約として切り分けることを推奨しています。
ステップ1:PoC契約(アジャイル型)
- 目的: あくまで「技術検証」と「相性確認」。
- 知財: PoCで生まれた成果物(レポートやPoC版ソフトウェア)は「共有」とする。ただし、お互いの既存のコア技術(バックグラウンドIP)には一切触れない(不実施権を確約)。
- ポイント: 「PoCで得たデータを使って、大企業側が勝手に類似サービスを開発しない」という競業避止を(短期間・狭い範囲で)入れることで、スタートアップ側の不安を払拭します。
ステップ2:本格的な共同事業契約(JVA)
- PoCが成功し、本格的に事業化(例:合弁会社設立)する段階になって初めて、ここで重い「知財の帰属」「ライセンス料」「収益配分」を交渉します。
PoCの段階で、まだ生まれるかもわからない「100億円の事業」の利益配分を議論しても意味がありません。まずは「小さく試す」ための契約を最速で結び、信頼関係を構築すること。法務・知財部門には、そのスピードを後押しする役割が求められています。
4. 結論:法務は「リスク評価」から「リスクテイクの設計」へ
イノベーションとは、不確実性(リスク)に挑戦することです。 これからの法務・知財部門に求められるのは、「リスクをゼロにすること(リスク評価)」ではありません。 「どのリスクなら取ってもよいか(=戦略的学習のためのコスト)」を経営陣や事業部と共に判断し、「万が一失敗しても、致命傷にならない仕組み(=撤退ラインの設計)」を契約書に落とし込むこと。
すなわち、「リスクテイクの設計(デザイン)」こそが、法務部門が果たすべき、最もクリエイティブなイノベーション支援なのです。


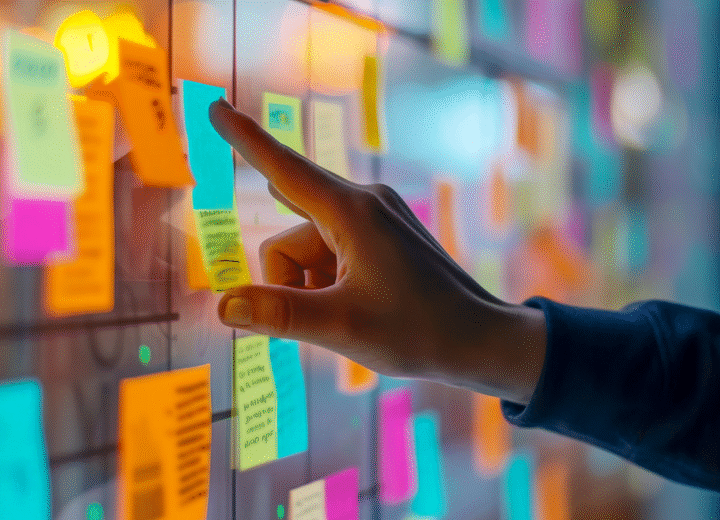





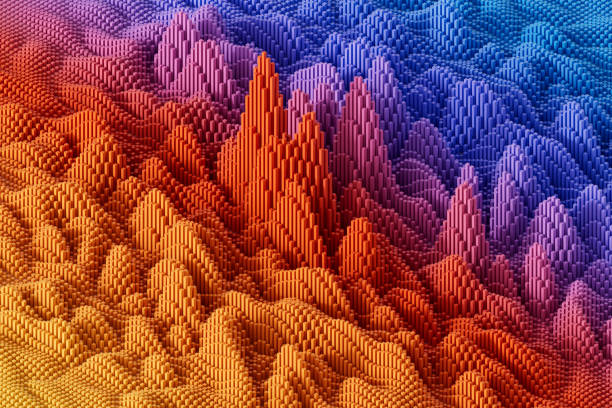

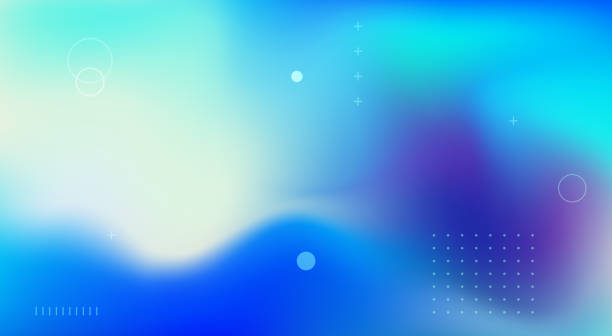



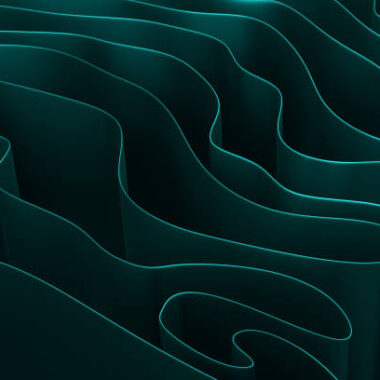




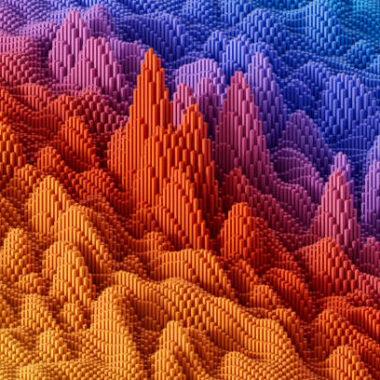


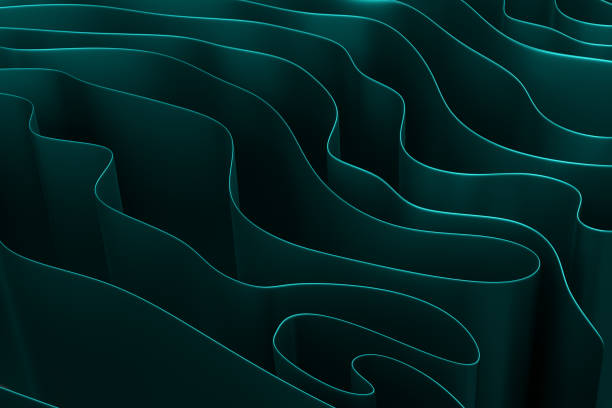


コメント