オープンイノベーションの必要性は誰もが語る。しかし、文化もスピードも異なる組織が「出会う」ことから「事業を創る」ことの間には、深い「死の谷(デスバレー)」が横たわっている。
今回、JOIAのビジネスマッチング(PARTNER)をきっかけに、ヘルスケアサービス「メディカルほねチェック」の共同開発・提供に至った、旭化成株式会社とMediplat株式会社のお二方をお招きした。
大企業のCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)担当者と、スタートアップのCEOは、いかにして障壁を乗り越え、協業を軌道に乗せたのか。その「実践知」に迫る。
<パネリスト>
- 旭化成株式会社 経営戦略本部 CVC室 鈴木 健太 氏
- Mediplat株式会社 代表取締役 CEO 田中 浩輔 氏
- 日本オープンイノベーション協会(JOIA)(ファシリテーター:青山)
1. 出会い:「なぜ、ウチと?」— 最初の違和感
JOIA(青山): 本日はありがとうございます。まず、お二方の出会いはJOIAのマッチングでしたが、最初の印象はいかがでしたか?
旭化成・鈴木氏: 正直に申し上げますと、当初、我々のヘルスケア領域の担当部署は「なぜ、Mediplatさんと?」という反応でした。我々は素材(マテリアル)や住宅(ホームズ)、そして医療機器(ヘルスケア)のハードウェアが強い会社です。Mediplatさんのような「オンライン診療プラットフォーム」というソフトウェアの会社とは、事業上の接点が見えにくかったのです。
Mediplat・田中氏: 私たちも同じです(笑)。旭化成さんからJOIA経由でお話をいただいた時、「なぜ、あの巨大な化学メーカーがウチと?」と。私たちのようなアーリーステージのスタートアップにとって、旭化成さんのような企業との協業は魅力的ですが、同時に「リソースを割いた結果、何も決まらずに終わる」という最も恐れるシナリオも頭をよぎりました。
JOIA(青山): そこがスタートですよね。我々が仲介したのは、旭化成さんが持つ「BtoBの広範な顧客網(例:企業の健康保険組合)」と、Mediplatさんが持つ「toCの機動力あるサービス開発力」が、将来の「予防医療」市場で必ずや補完関係になると判断したからです。
2. 「死の谷」:半年の停滞と「言葉の壁」
JOIA(青山): しかし、マッチングから実際の協業開始まで、半年ほど停滞した時期がありました。いわゆる「死の谷」です。何が起きていたのでしょうか?
Mediplat・田中氏: 「言葉の壁」と「時間の壁」ですね。私たちは「まずプロトタイプを作って市場に出し、フィードバックで改善しましょう」と提案しました。開発は3週間です、と。すると、旭化成さんの担当部署からは「そのサービスのリスク評価は?」「知財の帰属は?」「社内規定上、3週間の稟議はあり得ない」という反応が返ってきました。
旭化成・鈴木氏: 痛いところです…(苦笑)。CVC室の私自身は「まずやってみよう」と理解しているつもりでも、それを事業部に持ち帰ると「100点の安全確認」を求められる。事業部からすれば、万が一、旭化成のブランドで健康データを漏洩でもしたら、会社全体の信用問題になる。彼らの言い分も正しいのです。スタートアップが言う「リスク」と、私たちが言う「リスク」の定義が、全く違いました。
Mediplat・田中氏: その「リスク定義」のすり合わせだけで、数ヶ月が過ぎていきました。正直、この話はもう無理かもしれない、と諦めかけた時期です。
3. 突破口:「CVC室」の覚悟と「知財」の切り分け
JOIA(青山): その膠着状態を、どう突破したのですか?
旭化成・鈴木氏: 私たちCVC室の「覚悟」です。事業部を説得するのをやめました。代わりに、「全責任をCVC室が持つ」と宣言したのです。
JOIA(青山): と言いますと?
旭化成・鈴木氏: 具体的には、「実証実験(PoC)の初期予算は、事業部ではなくCVC室の予算で全額執行する」「知財やブランド利用は一旦切り離し、まずは旭化成の社名を伏せたクローズドな環境で、Mediplatさんのサービスとしてテスト運用する」という形に切り替えました。事業部にとっては「ノーリスク」な状態を作ったのです。
Mediplat・田中氏: あのご判断は本当にありがたかったです。私たちも「旭化成」というブランド名を借りるのが目的ではなく、まずは「サービスが本当に価値を生むか」を検証したかった。鈴木さんたちが社内の「防波堤」になってくれたおかげで、私たちは開発に集中できました。
JOIA(青山): まさしく【INSIGHT 1】で論じた「協業の作法」ですね。CVCが「戦略的学習」の予算を持ち、既存事業部の「免疫システム」からプロジェクトを守った。
旭化成・鈴木氏: はい。そしてそのクローズドな実証実験で「骨密度が低いユーザーに、早期の受診勧奨ができた」という具体的な成果(データ)が出た。この「動かぬ証拠」を持って初めて、事業部は「なるほど、これならウチの顧客(企業健保)にも提案できる」と、本気になってくれたのです。
4. そして今:「メディカルほねチェック」の未来
JOIA(青山): そして、旭化成さんが持つ骨粗しょう症領域の知見と、Mediplatさんのプラットフォームが組み合わさり、「メディカルほねチェック」が生まれました。
Mediplat・田中氏: 旭化成さんとの協業で、私たちはスタートアップ単独では決して得られない「信頼性」と「専門的な医学知見」を得ました。
旭化成・鈴木氏: 私たちは、Mediplatさんから「顧客にサービスを届ける圧倒的なスピード」と「アジャイルな開発文化」を学びました。これは、我々が社内で100回研修をやるよりも、よほど強烈な組織変革の起爆剤になっています。
JOIA(青山): まさしく「非対称な強み」の交換ですね。本日は、協業のリアルなお話をありがとうございました。


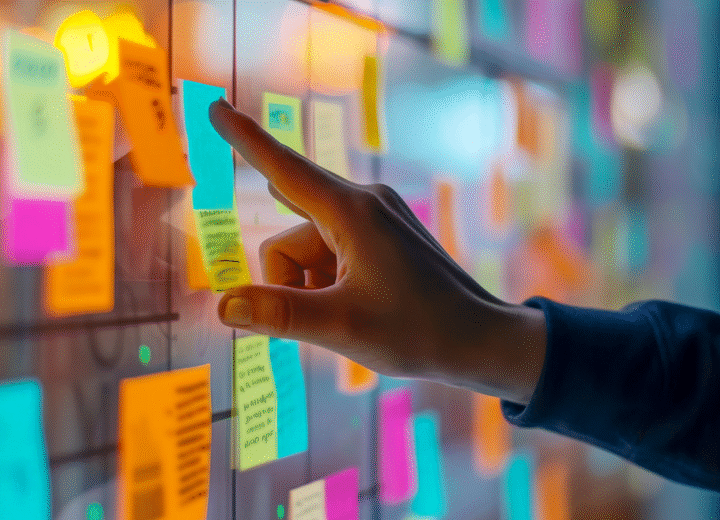
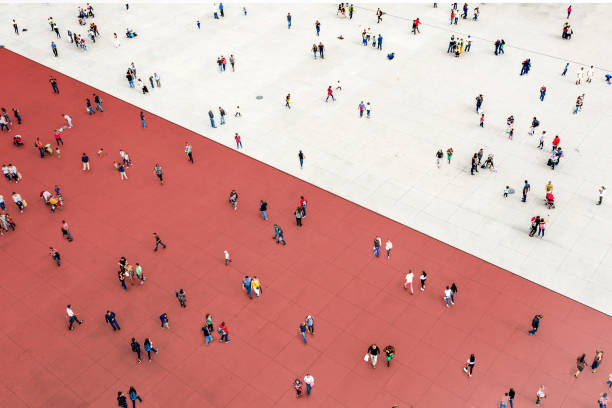

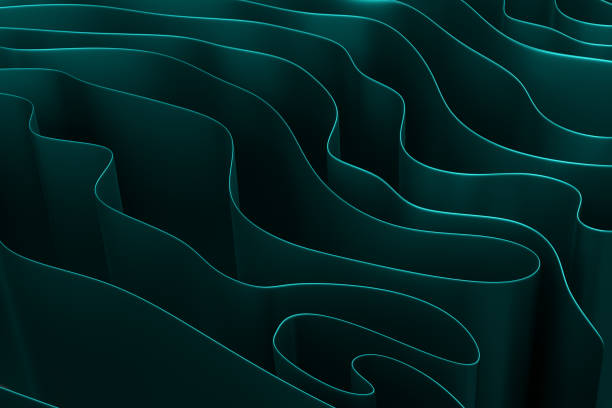

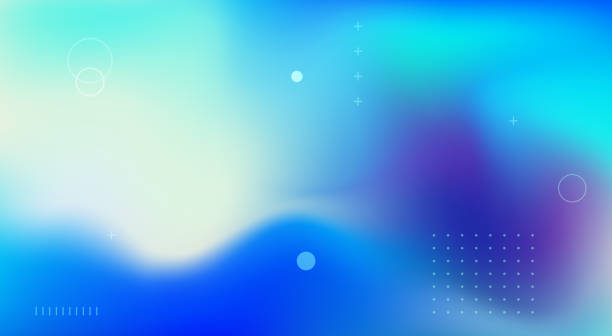






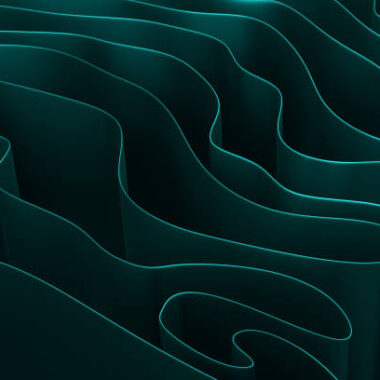
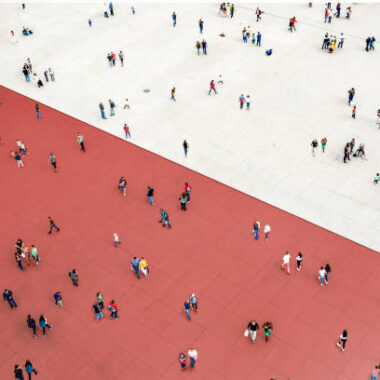
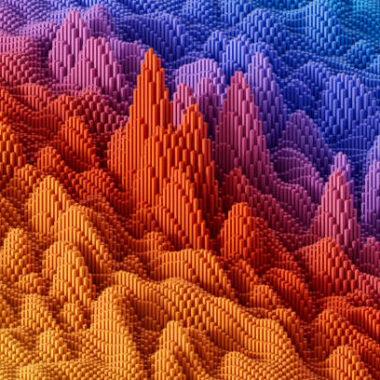

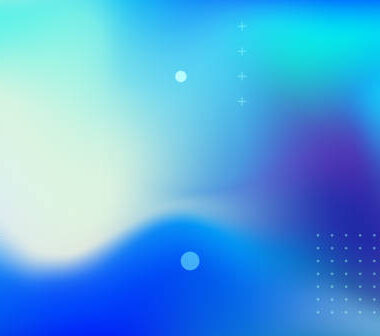



コメント