GX(グリーン・トランスフォーメーション)とサーキュラーエコノミー(循環型経済)への対応は、今やCSR(企業の社会的責任)の枠を超え、企業の存続を左右する中核的な経営アジェンダとなりました。
多くの企業が「資源循環」をテーマにオープンイノベーションを掲げ、スタートアップの持つリサイクル技術や新素材に関心を寄せています。しかし、デジタル分野の協業と同じ感覚で進めた結果、実証実験(PoC)ばかりで事業化に至らない「PoC死」が多発しているのも、また事実です。
なぜ、この分野の協業は失敗しやすいのでしょうか。
それは、サーキュラーエコノミーが「自社だけで完結できない」という本質的な特性を持つからです。デジタルの協業は1対1(例:大企業×スタートアップ)でも成立しますが、資源循環は「動脈産業(作る・売る)」と「静脈産業(集める・リサイクルする)」が両輪で回らなければ、絶対に成立しません。
失敗する協業は、この「静脈」の部分を見落としています。 本稿では、この「動脈」と「静脈」、さらには「異業種のインフラ」まで巻き込むことに成功したサントリーと三菱ケミカルの事例を分析し、成功の「勘所」を導き出します。
成功事例1:サントリー「ボトルtoボトル」— “静脈”と”インフラ”を巻き込む
サントリーホールディングスが推進する「ボトルtoボトル」水平リサイクルは、使用済みペットボトルを再びペットボトルとして再生する、最も難易度の高いサーキュラーエコノミーの一つです。
彼らの成功の鍵は、自社でリサイクル技術を開発すること(動脈)に固執しなかった点にあります。
- 勘所1: “静脈”(リサイクル業者)との徹底した協業 サントリーは、リサイクルの専門家である協栄産業と深く連携しました。協栄産業が持つ高度な再生技術を信頼し、サントリーは「再生ペットボトルの利用(=出口の担保)」にコミットしました。自社で工場を持つのではなく、「餅は餅屋」のパートナーシップを構築したのです。
- 勘所2: “異業種インフラ”(生活導線)の活用 最大の課題は「高品質なペットボトル」の「安定的な回収」です。サントリーは、この課題を解決するために、JR東日本や三菱地所といった、自社とは全く異なる「インフラ企業」と組みました。 駅(エキナカ)やオフィスビルといった「生活導線」に専用の回収ボックスを設置することで、消費者の利便性を損なうことなく、高品質な原料を安定的に確保する「仕組み(エコシステム)」を構築したのです。
もしサントリーが「自社の自動販売機の横にだけ」回収ボックスを置いていたら、このエコシステムは実現しなかったでしょう。彼らは「動脈」と「静脈」、そして「インフラ」を繋ぎ合わせる「ハブ」として機能したのです。
成功事例2:三菱ケミカル「マテリアル」— “川下”と”市場”を同時に創る
素材メーカーである三菱ケミカルもまた、GX/サーキュラーエコノミーの先進企業です。彼らの戦略は、「良い素材(動脈)」を作るだけでなく、その「使い道(市場)」と「リサイクル経路(静脈)」までを設計する点にあります。
- 勘所1: “川下”(ユーザー)と組んでケミカルリサイクルを推進 三菱ケミカルは、ペットボトルのケミカルリサイクル(化学的に分解し、新品同等の原料に戻す技術)において、キリンホールディングスと協業しました。 「技術はできたから誰か使ってくれ」ではなく、飲料メーカーという「大口のユーザー」と最初から組むことで、「技術開発」と「市場(出口)の確保」を同時に行ったのです。
- 勘所2: “異業種”(アパレル)と組んでバイオマス素材を普及 植物由来のバイオマス素材「ソアロン」の普及においても、アパレルメーカーの日清紡テキスタイルと連携。素材メーカーが「BtoB」の論理に留まるのではなく、最終製品(アパレル)の「BtoC」の価値(環境配慮、着心地)までを共同で訴求し、市場を創り出しました。
結論:GX協業の勘所は「エコシステム・デザイン」にある
サントリーと三菱ケミカルの事例から明らかなように、GX/サーキュラーエコノミーの協業で失敗する企業は「1対1の技術連携」として捉え、成功する企業は「多対多のエコシステム・デザイン」として捉えています。
この分野の協業を成功させる「勘所」は、プロジェクトの開始時に、以下の「3つのパートナー」を特定することです。
- 「動脈」パートナー(技術): スタートアップの革新的技術、自社の生産能力など。
- 「静脈」パートナー(回収・再生): 専門のリサイクル業者、廃棄物処理業者など。
- 「インフラ/市場」パートナー(場・出口): 鉄道、不動産、小売、あるいは川下のユーザー企業。
これらの「点」を「線」で結び、循環する「円」としてデザインすること。これこそが、GX/サーキュラーエコノミーにおけるオープンイノベーションの核心です。
私たち日本オープンイノベーション協会(JOIA)は、この複雑な「エコシステム・デザイン」を支援します。単なる1対1のマッチング(PARTNER)に留まらず、業界を横断した利害関係者の「場」(PLATFORM)を提供し、社会課題解決型の「プログラム」(PROGRAM)を推進することで、貴社のGX戦略を成功に導きます。


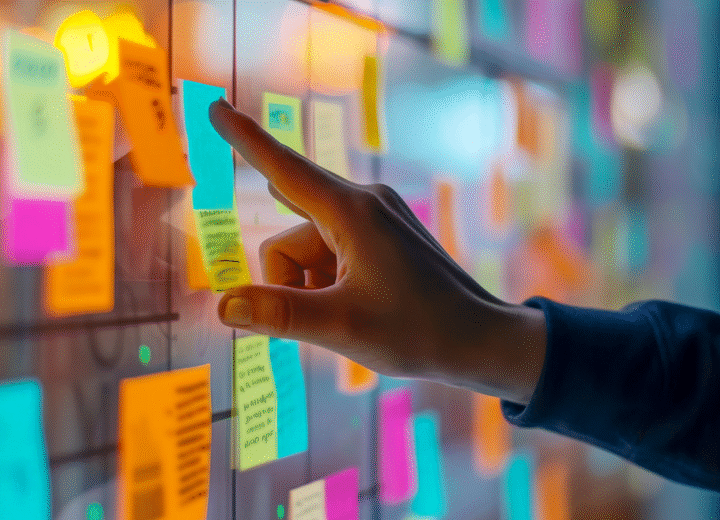



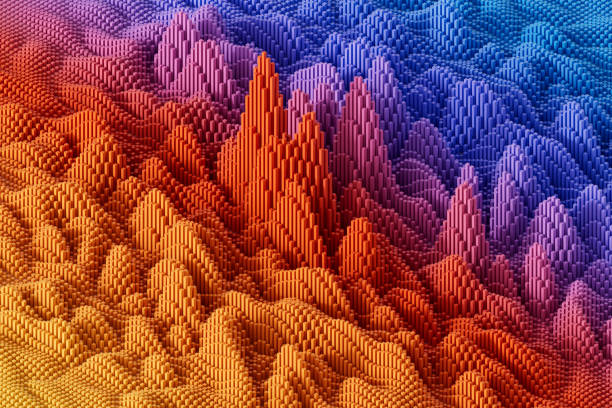
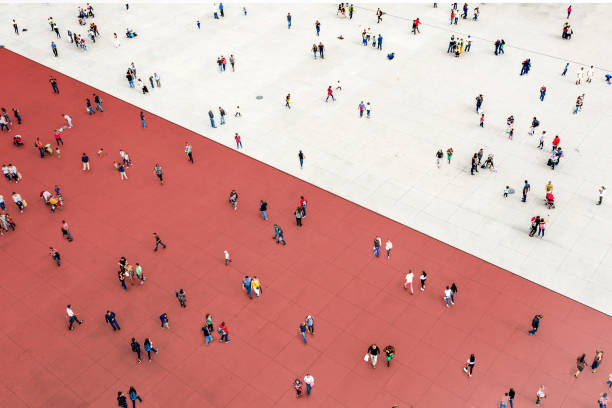
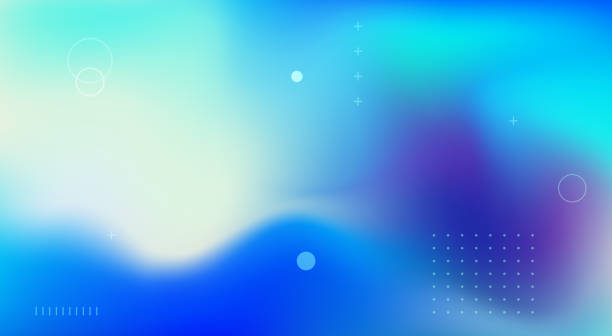





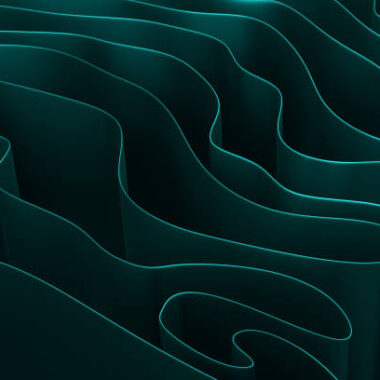


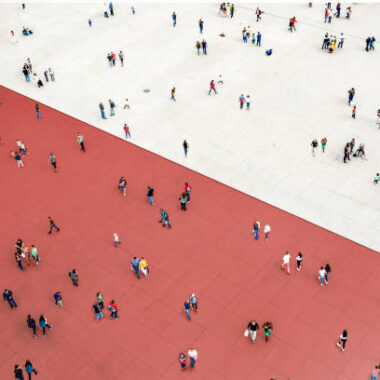



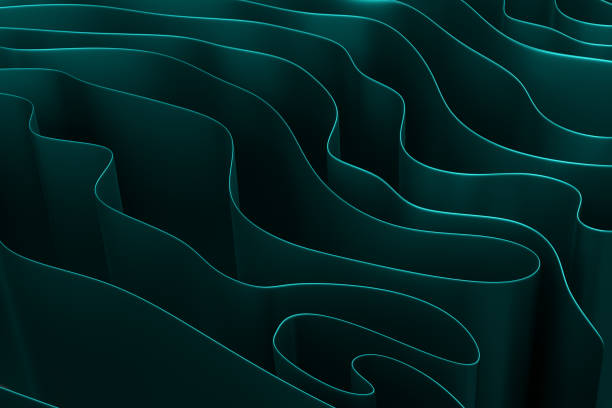




コメント