これまで、「目的」「契約」「プロジェクト運営」における、ガイドブック(教科書)と実践のギャップを見てきた。しかし、なぜ「自前主義」がはびこり、「法務部」が壁となり、「既存事業部」が抵抗勢力となるのか。
それらはすべて、「組織文化」という名の土壌に根ざした問題です。
オープンイノベーション(OI)のガイドブックも、その結論として「組織文化」や「経営陣のコミットメント」の重要性を説きます。しかし、その「正論」こそが、イノベーションを阻む最大の罠かもしれません。JOIA(日本オープンイノベーション協会)が導き出した、OIの成否を分ける「最後の結論」です。
【教科書の解説】:「組織文化」と「経営陣のコミットメント」
多くのガイドブックは、OIの成功要因として、手法論を超えた「組織文化」の重要性で締めくくられます。
- 組織文化づくり: 失敗を恐れず挑戦を奨励する文化、多様性を受け入れる風土が重要である。
- 経営陣のコミットメント: OIは既存事業との軋轢を生むため、経営陣が「本気でやる」という強い意志を示し、トップダウンで推進することが不可欠である。
これらは100%正しい「正論」です。しかし、JOIAが現場で見る現実は、この「正論」を振りかざすだけでは、組織が1ミリも動かない姿です。
【JOIAの付加価値】:ガイドブックの”外”にある「文化」の正体
教科書が示す「あるべき論」と、現場の「現実」の間には、深い溝があります。JOIAが長年の実績から確信する、実践的な結論は2つです。
示唆1:経営陣の”本当の”コミットメントとは何か
「イノベーションをやれ」と号令をかけ、「予算」をつける。多くの経営陣が、これを「コミットメント」だと誤解しています。
しかし、記事4で述べたように、プロジェクトが「既存事業部」の抵抗に遭った時、経営陣がその抵抗勢力の声(=短期的な売上)に配慮し、OI担当の梯子を外すケースを、私たちは何百と見てきました。
JOIAが問う**「”本当の”コミットメント」**とは、現場(OI担当)に以下の2つを明確に与えているか、です。
- 「失敗する権利」: 「賢明な撤退(記事4参照)」である限り、その失敗は咎めない、むしろ学んだことを評価する、という明確な保証。
- 「既存事業部への介入権限」: 「我が社の未来のために、既存事業の”聖域”に踏み込んででも、この変革を推進せよ」という、経営陣が持つ「介入権限」の委譲。
「予算」は出すが「失敗」は許さない。「権限」は与えず「既存事業部を説得しろ」と言う。これが、イノベーションが起きない組織の典型です。
示唆2:結論は「個の熱意」と「場の設計」
本連載を読んで、皆様は「OIとはなんと面倒なものか」と思われたかもしれません。 その通りです。ガイドブックという「手法(How)」を学ぶだけでは、イノベーションは絶対に起きません。
JOIAが長年の伴走支援で確信している、ただ一つの真実。 それは、結局のところ、イノベーションを突き動かすのは**「個の熱意」**――「これを何としても実現したい」という担当者の(あるいは経営者の)狂気にも似たパッション――でしかない、ということです。
そして、JOIAのような組織の役割は、その「熱意」の火を消さない、むしろ燃え上がらせる**「場の設計」**を行うことです。
記事3の「攻めの契約ルール」も、記事4の「既存事業部との溝を埋める仕組み」も、そしてこの記事5の「失敗する権利」も、すべてはその「個の熱意」を守り、育てるための「場の設計」に他なりません。
結論(連載の総括)
オープンイノベーションのガイドブック(教科書)は、進むべき道を示す「地図」として非常に重要です。
しかし、その「地図」だけを持っていても、現場で起きる「嵐(=組織の抵抗)」を乗り越えることはできません。
JOIAが提供するのは、その「地図(手法)」の先にある、「嵐」の中でどう進むかという「実践(リアル)」の知恵です。 イノベーションの成否は、手法を「知っているか」ではなく、「個の熱意」を「組織として受け止められるか」にかかっています。
JOIA(日本オープンイノベーション協会)は、その「実践」の場にこそ、皆様と共にありたいと願っています。


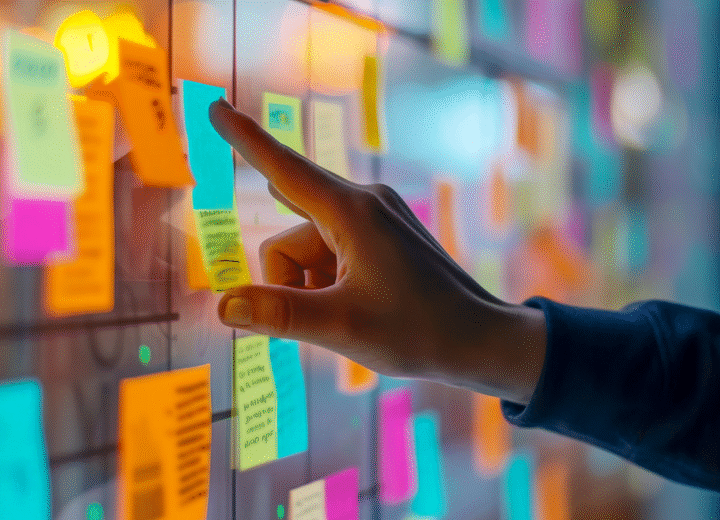

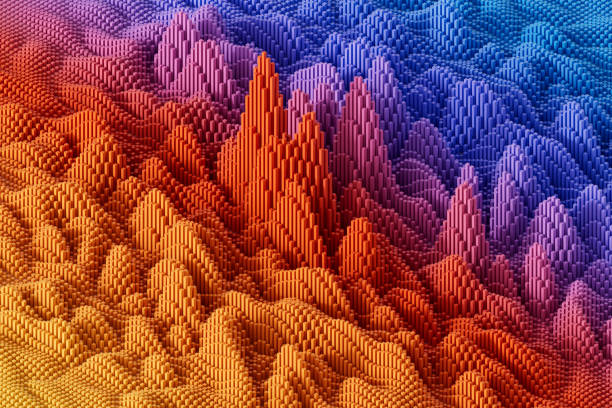




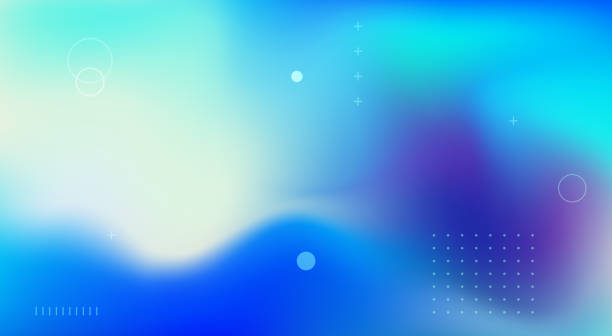

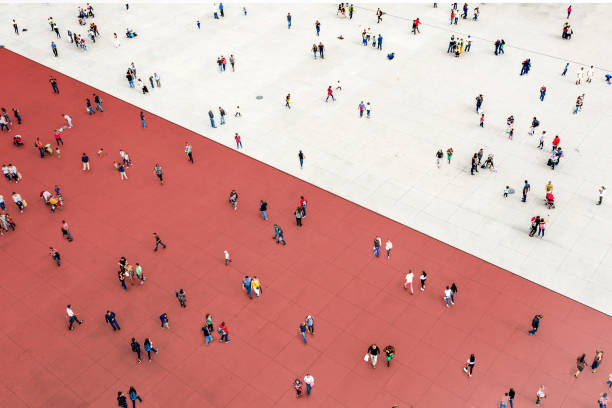



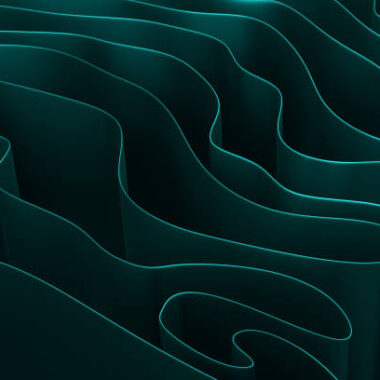




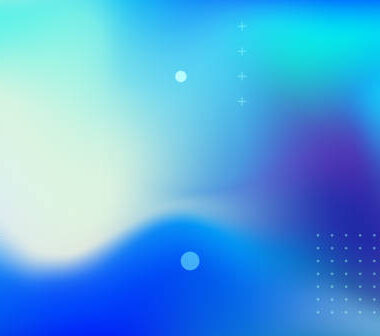


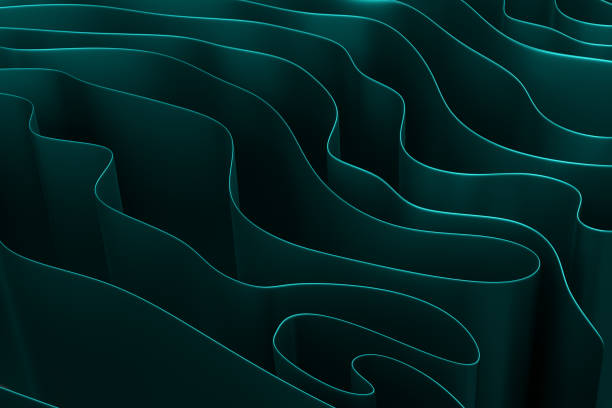


コメント