オープンイノベーション(OI)の「目的」を定めた後、次に「誰と組むか」というパートナー探索が始まる。ガイドブックはピッチイベントやCVCの活用を推奨するが、多くの大企業が”流行りのスタートアップ”を訪問するだけの「観光」で終わっている。JOIAの実践から、真のパートナーを見つけるための本質を問う。
【教科書の解説】パートナーシップ構築の「型」
『実務者のためのオープンイノベーションガイドブック』のような教科書では、パートナーシップ構築の手法として、一般的に以下のような「型」が紹介されます。
- ピッチイベントへの参加: スタートアップが集まるイベントに審査員や聴衆として参加し、有望な技術を探す。
- CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)の設立: CVCを立ち上げ、戦略的リターンを期待してスタートアップに投資・接触する。
- ニーズの発信: 自社のウェブサイトやイベントで「当社はこういう技術を探しています」と公募(リバースピッチ)する。
これらは、外部と接点を持つための有効な手段(How)です。 しかし、JOIAが懸念するのは、この「型」をなぞらえること自体が目的化し、**最も重要な「質」**が見失われている点です。
【JOIAの付加価値】教科書が触れない「2つの罠」
JOIAは、大企業と多様なパートナーとの「出会いの場」を数多く設計してきました。その経験から、パートナー探索における深刻な「2つの罠」を指摘します。
罠1:「探索」が「有名スタートアップ詣で」に陥る
これが最も多い失敗です。 OI担当部署が、経営陣への「分かりやすい成果報告」のために、メディアで話題の有名スタートアップや、著名な大学の研究室ばかりを訪問する。 私たちはこれを**「スタートアップ観光(ツーリズム)」**と呼んでいます。
彼らは本当に貴社のパートナーでしょうか? 流行りの技術(T)に飛びつくだけで、自社の課題(D)や事業(B)とどう結びつくのか、深い洞察がない。
JOIAが実践で確信しているのは、真に価値あるパートナーは、往々にして”泥臭い”場所にいる、ということです。 それは、まだ世に知られていない地方の大学かもしれませんし、既存の取引先である中小企業(サプライヤー)が持つ、見過ごされてきた技術かもしれません。
「流行り」を追うのではなく、自社の「目的」に立ち返り、**「意図せぬ出会い(セレンディピティ)」**をいかに設計するか。それこそがOI担当者の腕の見せ所です。
罠2:「選ぶ」側から「選ばれる」側へ
もう一つの罠は、大企業側の「無意識のプライド」です。 「パートナーを評価してやる」「有望なら買ってやる」 こうした「上から目線」に陥っていないでしょうか。
しかし、現実は逆転しています。 優秀なスタートアップや研究者は、協業相手(大企業)を選んでいます。 彼らが大企業に求めるのは、単なる「お金」ではありません。「素早い意思決定」「実証実験(PoC)のフィールド提供」「既存事業のアセット(販路やデータ)の解放」です。
「検討します」と持ち帰るだけで半年間も返答がない大企業。 「NDA(秘密保持契約)が…」「知財が…」とリスクばかりを主張する大企業。 こうした企業は、**「選ばず」ではなく「選ばれない」**のです。
ガイドブックは「どう探すか」を教えますが、JOIAは**「いかにして”選ばれる”パートナーになるか」**こそが重要だと考えます。それには、自社の「弱さ」を開示し、相手に「アセット」を差し出す覚悟が問われます。
結論
パートナー探索とは、「流行りの技術」を探すことではありません。 自社の「目的」に照らし、**「誰と組めば、お互いが”選ぶ”に値する価値を提供できるか」**を見極める、極めて戦略的な活動です。
教科書通りのピッチイベントに参加する前に、まず自問すべきです。 「私たちは、パートナーから”選ばれる”準備ができているか?」と。
次回は、パートナーと出会った後の最大の難関、「契約・知財」の壁について解説します。


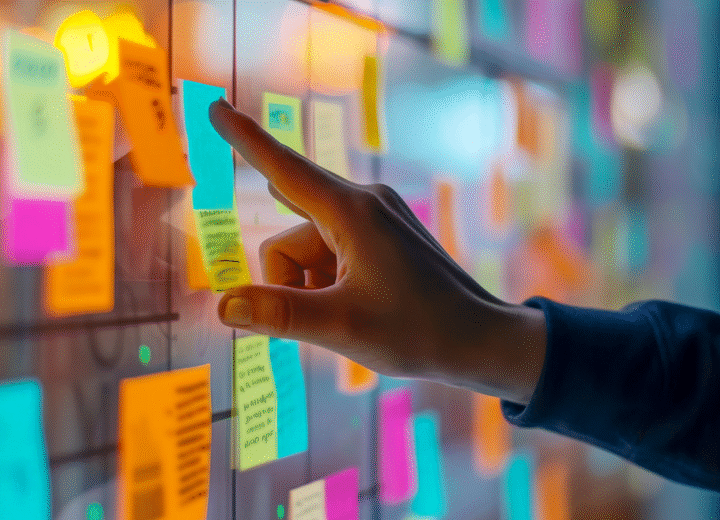






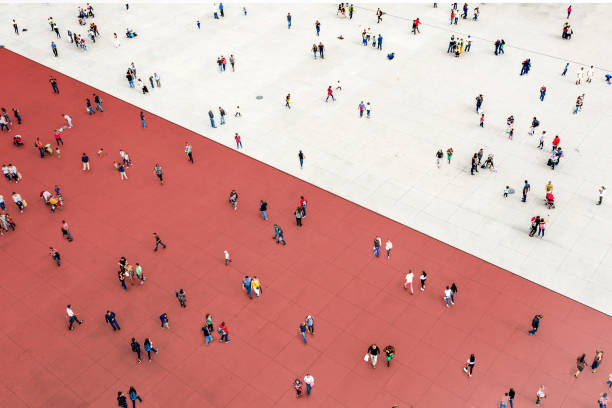




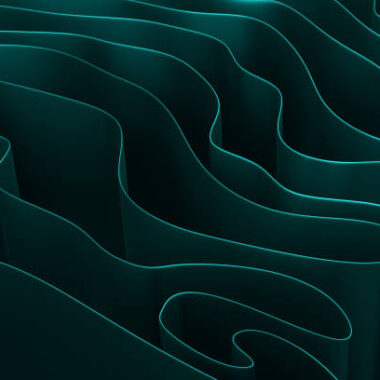




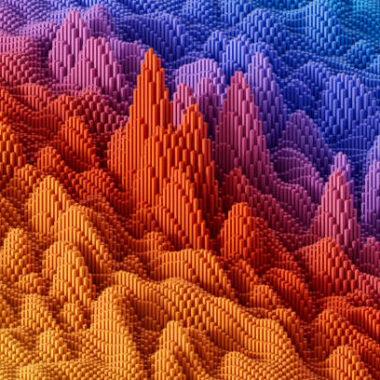
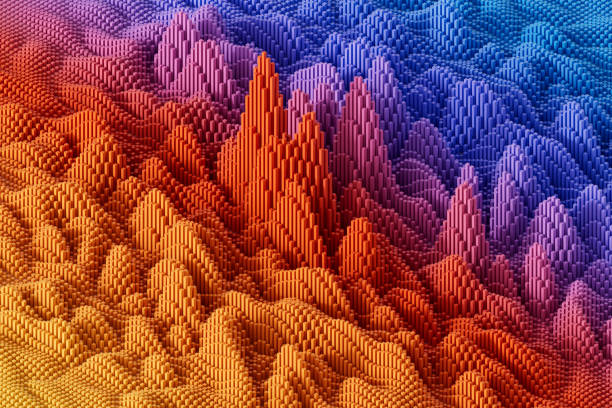
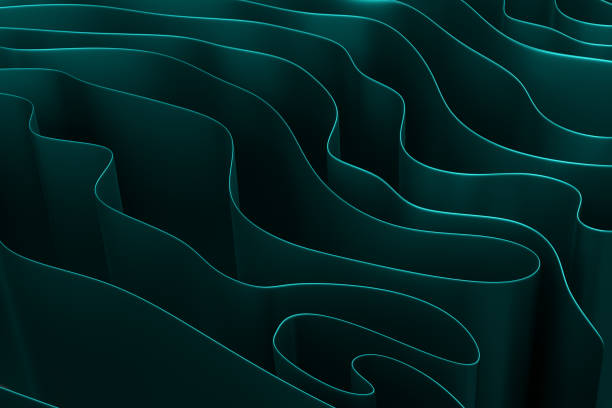


コメント