『魂ある戦略』はいかにして大企業の壁を越えるか ― SaaSとコンサルティングを融合させる「ハイブリッド事業」の実践論
■ なぜ、日本の大企業の新規事業は、実行段階で失速するのか?
インタビュアー: 「本日はお忙しい中ありがとうございます。青山さんは20年以上にわたり、大企業、スタートアップ、コンサルと様々な立場で新規事業に携わってこられました。多くの新規事業が、緻密な戦略を持ちながらも、現場での実行に至らず失速してしまう最大の要因は、どこにあるとお考えですか?」
青山 武史: はい、それは多くの企業が直面する、根深い課題ですね。私の結論から申し上げますと、失敗の最大の要因は、緻密に練られた**「戦略(ロジック)」と、それを動かす現場の「組織(ビジョン)」**との間に存在する、深い断絶にあると考えています。
素晴らしい事業計画書も、実行する人々の情熱や納得感がなければただの紙切れです。逆に、情熱だけのビジョンも、それを支える持続可能なビジネスモデルという骨格がなければ、すぐに燃え尽きてしまう。私のキャリアは、この断絶を乗り越え、戦略に魂を吹き込み、ビジョンに骨格を与える、その方法論を常に「当事者」として探求する旅でした。
■ ハイブリッド事業の核心 ― プロダクトとコンサルティング、2つの体験価値をどう融合させるか
インタビュアー: 「非常に示唆に富むお話です。今、多くの大企業が、まさにその『戦略と組織』を繋ぐものとして、SaaSプロダクトと人によるコンサルティングサービスを組み合わせた、ハイブリッドな新規事業を模索しています。しかし、この2つの異なる体験価値を継続的に提供し、事業として成功させるのは非常に難しい。この挑戦を成功させるための『要件』と『方法論』について、お考えをお聞かせください。」
青山 武史: 素晴らしいご質問です。その問いこそ、この領域の事業開発における核心です。成功の鍵は、プロダクトとコンサルティングを「足し算」でなく、「掛け算」の関係として、一つのジャーニーとして設計することにあります。そのための要件は3つあると考えています。
第一に、プロダクトが『問い』を生み、コンサルが『答え』に導く設計であること。 SaaSプロダクトの役割は、単なるデータ可視化、つまり「健康診断の結果」を見せるだけでは不十分です。データに基づき、顧客組織が自ら向き合うべき、本質的な「問い」、例えば「なぜ、このチームのエンゲージメントだけが低下しているのか?」といった問いを突きつける、言わば「MRI」のような診断装置でなければなりません。そしてコンサルティングの役割は、その「問い」を基点として、対話やワークショップを通じ、顧客自身が腹落ちする「答え(アクションプラン)」を見つけ出すプロセスを設計し、伴走することです。
第二に、体験価値の『フライホイール』を回すこと。 この2つがうまく連携すると、価値が好循環し始めます。「SaaSデータで課題が可視化される → コンサルティングで課題が解決され、成功体験が生まれる → 成功体験によって、SaaSプロダクトへの信頼と活用意欲が高まる → 活用が深化し、新たな課題がデータで見つかる…」というサイクルです。このフライホイールが回り始めると、顧客の成功体験が積み上がり、事業は自律的に成長していきます。
第三に、スケーラブルな『型』と、個別最適な『芸』の両立です。 事業の収益性を担保するには、コンサルティングサービスを「商品化」する必要があります。そのために、再現性の高いワークショップの標準パッケージや、コーチングのフレームワークといった「型」を開発します。一方で、真に顧客の変革を実現するには、専門家がSaaSデータに基づいて、その「型」を柔軟に応用・カスタマイズする、いわば職人芸の「芸」も不可欠です。この両立こそが、事業の品質と収益性を同時に高める鍵となります。
■ YKK APでの実践 ― 壮大な構想を、いかにして現実に落とし込んだか
インタビュアー: 「非常に明快な方法論ですが、それを大企業の中で実現するのは簡単ではないはずです。YKK APという伝統的な『モノづくり』企業で、SaaS事業と組織開発を両輪で推進されたご経験について、具体的に聞かせてください。」
青山 武史: おっしゃる通り、最も困難だったのは、プロダクト開発そのものよりも、むしろ社内の文化や制度といった「見えない壁」との対峙でした。成功体験を持つ既存事業部のプライド、短期的なP&Lを重視する評価制度、前例のないものへの抵抗感。これらは、変革を目指す大企業が必ず直面する課題です。
私は、この壁を乗り越えるために、大きく2つのアプローチを取りました。一つは、SaaS事業を、いわば社内の「スタートアップ」として扱い、徹底的にスピードを重視すること。もう一つは、そのスタートアップが育つための「土壌」、つまり会社全体のOSを書き換えることです。
具体的には、新規事業の特性に合わせて品質基準などを柔軟化する「特区」制度を経営陣に提案し、導入しました。また、P&Lだけでは測れない新規事業の価値を正しく評価するため、第三者機関による事業価値評価の仕組みも構築しました。さらに、この挑戦を担う専門家として「ビジネスデザイン職」を定義し、新たな採用・育成プロセスも立ち上げました。
同時に、point0での共創活動のように、社外のパートナー、時には競合他社すらも巻き込み、「業界全体の課題解決」という、より大きなビジョンを共有することで、社内の抵抗感を乗り越える推進力を得ていきました。それはまさに、事業戦略と組織戦略を同時に、かつ一体として動かす、実践の連続でした。
■ 結論:未来を創るチームとは
インタビュアー: 「最後に、青山さんが考える、これからの時代に本当に価値を生み出す『チーム』とは、どのような姿でしょうか?」
青山 武史: はい。私が考える、これからの時代に本当に価値を生み出すチームとは、企業のビジョンと、メンバー一人ひとりの「こうありたい」という想い(WILL)が、重なり合っているチームです。
心理的安全性が担保された場で、誰もが自律的に挑戦し、その挑戦から得た学びが、個人の成長と事業の進化の両方に繋がっていく。
結局のところ、企業の持続的な成長の源泉は、そこにいる人々の創造性が、いかに解放されているかの一点に尽きます。この考え方は、企業で掲げるパーパスに含まれる傾向にあります。企業の「はたらく」を豊かにするという使命を持ち、その最前線で活躍していきたい。そう強く願っています。
インタビュアー: 本日はありがとうございました。お話を伺い、多くの日本企業が直面する新規事業の課題の本質が見えた気がします。それは、「緻密な戦略」と、それを実行する「生きた組織」との間にある深い溝です。
青山さんが提示された、SaaSプロダクトとコンサルティングを融合させる「ハイブリッド事業」という処方箋、そしてデータが「問い」を生み、人が「答え」に導くという設計思想は、この溝を埋めるための極めて具体的で、実践的な方法論だと感じました。
そして何より印象的だったのは、そのすべてを語る青山さんご自身が、評論家ではなく、常に「当事者」として変革の渦中に身を置いてこられたという事実です。その言葉には、大企業の変革を成功に導いてきた実践者ならではの重みがありました。日本のビジネス界が今まさに必要としているのは、このような『魂ある戦略』を実装できるリーダーなのかもしれません。本日は、誠にありがとうございました。
青山 武史: こちらこそ、ありがとうございました。本日のお話が参考になりましたら幸いです。

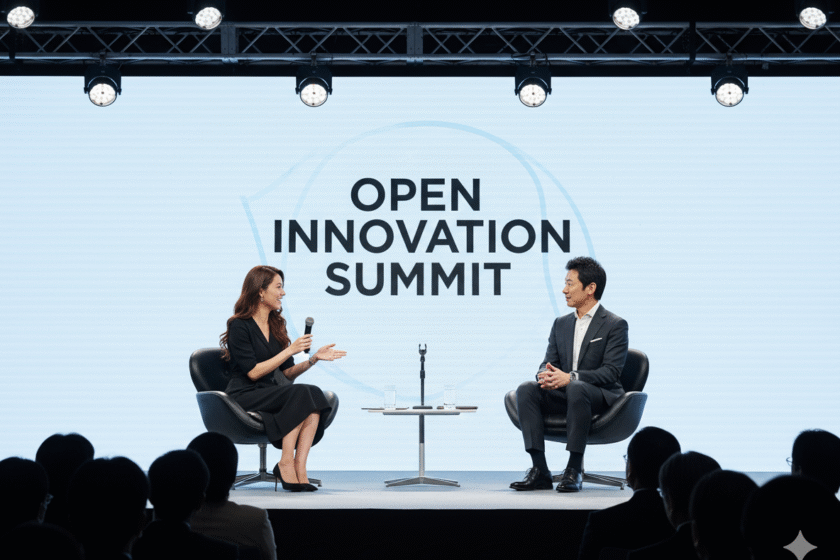
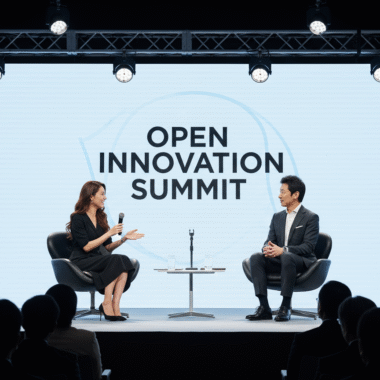





コメント